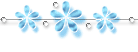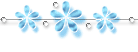|
* とある花屋の日常 *
いつもの朝。
今日も同じ朝。
昨日も、明日も。必ず、朝はやってきます。
朝の7時に、わたしは決まって目を覚まします。
何もなくても、勝手に体が起きてしまうのです。
それは、同じ生活をずっと続けてきたから。
決まった時間に寝て、決まった時間に起きる。
大好きなお花と、大切な友達に囲まれて暮らす、今の生活を。
「……ふわ……」
体を起こしてあくびをすると、わたしは後ろを振り向きます。
そこには、家族全員が幸せそうに笑っている写真を飾っています。
何枚もある中の、一番好きな写真。
「おはよう。お母さん、お父さん」
わたしは、いつもと同じ笑顔で、写真の中の両親に言いました。
外に出ると、それはもうこれでもかというくらいの快晴だった。
太陽の光は眩しく、吹き抜ける風が雲を流す。
街はたくさんのネコで賑わっており、客引きをする声や、挨拶を交わすネコたち、笑顔でパトロールをするギルドネコの姿もあった。
今日もこの街は平和で、のどかだ。
表通りの小さな花屋【Mel Flower】。
店舗兼住宅で、1階が店舗部分、2階が住宅部分となっている。
ピンクと白を基調としたデザインで、装飾も可愛らしく、たとえ花に興味がなくとも、足を止めてしまいそうになる、綺麗な店だった。
店主を務める彼女の名はメレディス・アイメルト。
青いセミロングの毛先がくるりと縦ロールになっていて、動くとふわりと揺れた。
大きなネコ耳の下には、花飾りがついた小さな赤いリボンを結んでいる。黒いケープに、ピンクのワンピースの裾からは黒いスカートと長い尻尾が覗き、白の
ロングブーツを履いた、いつも明るく、笑顔を絶やさない、そんなネコだった。
年は19と、まだ若いのだが、この世界では若者が店を営んでいることが珍しくないようだ。
彼女はよく、というか常に笑っている。
店に友達が来れば笑顔で応対し、別れ際も笑顔でまたねと手を振る。
普通のネコならばこれは怒るだろうという出来事があったとしても、彼女の笑顔は崩れない。
周りの彼女に対するイメージは、『いつも笑顔の幸せそうなネコ』だった。
メレディス本人も、そう思っていることだろう。
毎日が楽しくて、幸せだと。
「うーん……ちょっと栄養が足りないかなぁ……」
その花に合った肥料を与え、毎日汲み上げている綺麗な地下水をやり、彼女は立派に『花屋』を務めていた。
母親の姿を見て、自分で勉強をして。周りの力を借りて。
そして再びこの店を開いて、早4年。
働く姿も様になっており、常連もたくさんできた。けして多くはないが、友達もよく遊びに来てくれている。
「……これでよし、っと」
そんなこの店を、メレディスは何よりも大切に思っていた。
大切だからこそ、なくしたくなかった。
両親が愛したこの場所を守りたい。
自分が育った家で暮らしていきたい。
その思いで、ここまでやってきた。
今日も、のんびりと時間が過ぎてゆく。
花屋はそれほど忙しくなる業種ではないので、メレディスもゆったりと過ごしていた。
時計の針が午後3時を指し、お茶にしようかと思ったとき、
「お邪魔するのだわ」
鈴のような声が、店に響いた。
メレディスにとっては聞き慣れたその声は、彼女の幼馴染の声だ。
「アルヤ。トリスも」
椅子から立ち上がったメレディスは、笑顔で二人に歩み寄った。
店に訪れたのは、背の小さいネコと、背の高いネコ。
対照的な二人だが、メレディスを見つめる眼差しは、どちらも同じ、優しい瞳だった。
「メレ! ケーキ買ってきたのだわ!」
「わぁ、ありがとう♪」
アルヤと呼ばれた背の小さいネコ。名はアルトマイヤー・リヴィエール。腰ほどの長い金髪をツーサイドアップに黒いリボンでまとめている。ギルドの仕事を
する時は髪を下ろして帽子をかぶるので、今は自由時間ということになる。
ネコのマークがついたネクタイに、赤いチェックのスカート、ぶかぶかのアームウォーマーと、制服なのかよく分からない着こなしをしているのだが、アルト
マイヤー本人は気に入っているらしい。
特徴的な喋り方をするが、二人はとっくに慣れているので、気にした様子は一切ない。
それほど大きくないメレディスより更に10cmほど背が低いので、年齢の割に子供に見られることがしょっちゅうだ。
その度にアルトマイヤーは背中の鞭を抜こうとするのだが、それはメレディスが止めているらしい。
「メレは今日も愛らしいわね」
「当然なのだわ」
「そ、そんなことないよ」
トリスと呼ばれた背の大きいネコ。名はベアトリス・ボールドウイン。長い銀髪を後ろでまとめ、横髪は切りそろえられている。高い身長と細い目つきで、三
人の中では最年長だった。
黒い袖なしシャツに、紫のロングスカート。そして半透明のケープを常に纏い、小脇に抱えるは本と、魔法が得意な彼女をよく表した衣装だった。ちなみに
シャツの胸元は結構開いている。
腕につけたブレスレットの一つに、メレディスの髪飾りと、アルトマイヤーのチョーカーについているものと同じ、ピンクの花飾りがついている。三人の友情
の証、とかなんとか。
「今日は……そうね、ローズヒップがいいのだわ」
「うん。淹れてくるから、二人は座っててね」
「いつもありがとう。お礼と言っては何だけど、新作のケーキにしたわ」
「わーい♪」
幼馴染ということもあり、三人の付き合いは幼少の頃から続いている。
違うのは、メレディスは店を営む街ネコで、アルトマイヤーとベアトリスは街を守るギルドネコだということだ。
ギルドネコは街を守るという仕事柄、基本的に戦闘力のあるネコがなるものなので、未熟な水魔法しか扱えないメレディスには不向き。そもそもメレディス
は、幼い頃から両親の店を継ぐことしか考えてこなかったので、その選択肢ははじめからなかった。
そんなメレディスの父親は、名高いギルドネコだったという。この花屋は、メレディスの母親が開いたものだ。
一緒に仕事をする二人を羨ましく思うことはあるが、休憩やちょっとした依頼のついでにいつも店に立ち寄ってくれるので、寂しさは感じなかった。こうして
ケーキを買ってきてくれたり、面白い話を聞かせてくれたりするのが、メレディスは嬉しかったからだ。
「……甘いのだわ」
生クリームがたっぷり乗ったケーキを一口食べたアルトマイヤーは、神妙な面持ちで言った。
「ケーキだもの、そりゃ甘いわよ」
「アルヤにはちょっと甘すぎたかな?」
さも当然とばかりに言葉が返ってくる。
アルトマイヤーは、可愛らしい見た目に反して甘いものがそれほど得意ではなかったりした。
「まるで砂糖をそのまま食べているかのようなのだわ……」
「くす、大袈裟ね」
言いつつ、食べるのを止めないアルトマイヤー。ケーキ屋だからといって甘いケーキばかりではないし、ビターチョコケーキなども売っているのだが、彼女は
いつも同じケーキを3つ買うことにこだわっている。
一口食べては紅茶を飲み、といった行為を繰り返していると、
「アルヤ、わたしのイチゴ食べる?」
「食べるのだわ!」
メレディスが、にこりと笑いながら、アルトマイヤーの皿に自分のイチゴを載せた。
けしてイチゴが嫌いなわけではない。ただ、彼女が自分のためにケーキを買ってきてくれたのだからという気持ちからだ。
アルトマイヤーは、『三人』で、『同じ』ものを食べたいと、そう考えている。
幼い頃と違い、三人で一緒に居られる時間が減ってしまったことを寂しく思っているからだろう。
特に、メレディスの喜ぶ顔が見られるのなら、甘ったるいケーキくらい何個でも食べるだろう。
今日も、新作ケーキが出たとの情報を巡回中に聞いたため、ベアトリスを誘ってわざわざ遠いケーキ屋まで行ったのだ。
「……ありがと、アルヤ」
「?? イチゴをもらったのはあたしなのだわ」
メレディスの突然のお礼に、アルトマイヤーは困惑した様子で言った。
どうやら、言葉の真意が掴めなかったらしい。
「そしてそのイチゴはこっそり私が……」
アルトマイヤーの注意がイチゴから逸れたのをいいことに、ベアトリスがそっと自分のフォークをそのイチゴに伸ばしていた。すぐに気付いたアルトマイヤー
がすかさず反応する。
「待つのだわ! これはあたしのイチゴなのだわ!!」
この後、何故かイチゴ(Fromメレディス)の争奪戦が始まった。
勝敗は引き分け、というかメレディスがもう一つあったイチゴをベアトリスの皿に載せただけなのだが。
「ありがとう、メレ」
「なんとか守りきったのだわ……!」
二人は満足そうに、真っ赤なイチゴを頬張った。
それから、お祭りの話をしたり、最近あった事件の話、リーダーは今日も鬼畜だった話など、一時間ほどお喋りを楽しんだ後、アルトマイヤーとベアトリスは
仕事へ戻っていった。
僅かばかりの寂しさを感じつつ、午後の水やりをしようと、再びエプロンをつけた。
辺りが暗くなり始める頃が、この店の閉店時間だ。
メレディスは、全ての花の様子を見て、うんうんと頷き、閉店の準備を始めた。
やがてそれも終わり、シャッターを閉めようというとき、
「メレディス」
後ろから声がかけられた。こちらもまた聞き慣れた声だ。
振り返ると、彼女のもう一人の幼馴染、クライヴェルグが立っていた。
「あ、お疲れさま。久しぶりだね」
「今度は少し長引いた。これ、土産」
クライヴェルグが差し出した小さな包みを、メレディスは笑顔で受け取った。
「ありがとう」
「……ああ」
すらりと伸びた長身に、濃い紫の髪と、やや瞳が大きいが、端正な顔立ち。白い軍服に身を包んだギルドネコ、クライヴェルグ・エイジェルステット。通称ク
ライヴだ。ギルド内でも高い地位におり、アルトマイヤー、ベアトリスとはまた違った環境に身を置いている。
そのせいか、メレディスたちと会う機会は昔に比べてめっきり減り、こうして、仕事が終わった後の僅かな空き時間に来て、ちょっとした世間話をする程度に
なっていた。
ギルドネコであるアルトマイヤー、ベアトリスの二人は、仕事上たまに会うことはあるが、花屋を営む街ネコであるメレディスは、クライヴェルグ自身が出向
かないと中々顔を合わせることができないため、いつも『久しぶり』という挨拶を交わしていた。
「わぁ……きれいだね」
クライヴェルグがメレディスに渡したお土産は、薔薇を模った、薄いピンク色をしたチョコレートだった。花びら一枚一枚丁寧に作られており、まるで本物の
ようだった。最近街で流行っているらしい。
「好きだろ? チョコ。色々あったけど、一番人気って言うこれにしてみたんだ」
「うん、好き。嬉しいな」
メレディスの所に来るとき、クライヴェルグは必ず何か手土産を持って来る。お菓子だったりちょっとした装飾品だったり、本だったり。
しかし、決して本物の花は持って来なかった。
「よかったら、あがっていく?」
「いや、いい。時間があまりないんだ」
「そっかぁ」
「今日も、それを渡すために来たようなもんだ。今人気らしいから」
あまり表情を変えないクライヴェルグだったが、メレディスの前では、よく笑っていた。
それでも、幼い頃と比べると、笑顔でいる時間は減っていて、ギルドの忙しさを感じさせた。
「そうなんだ。初めて聞いたよ〜。違う種類のも見てみたいな」
「また時間ができたら、売ってる店に連れて行くよ」
「うん」
「……なぁ」
「なあに?」
クライヴェルグの問いかけに、メレディスは少しだけ首を傾げて答えた。
しかし、その先に言葉は続かず。
「?」
どうしたの、と言おうとしたメレディスの頭に、ぽんと手を置いて、そっと撫でた。
滅多に見せない優しい笑顔で。
「……元気そうで良かった」
「わたしはいつでも元気だよ。クライヴこそ、無理しすぎないでね?」
「ああ、気をつけるよ」
言いつつも、多忙な彼のこと、今日もこれからやることがあるのだろうが。
クライヴェルグは、一瞬だけ目を閉じ、息を吐き「じゃ、また」と言って踵を返したが、すぐに止まった。
「どうかした?」
メレディスの言葉に振り返ると、少しだけ言いよどんで、
「……また、来るから」
「うん。待ってるね〜」
恥ずかしそうに言うが、メレディスはいつもと同じ調子だ。
ああ、と微かに笑みをこぼすと、クライヴェルグは再び踵を返し、ギルドの宿舎へと帰って行った。
その姿を、メレディスは手を振りながら見送った。
今日も、いつもと同じ一日が終わりました。
平穏で、平凡な毎日。でも、幸せで、楽しい毎日。
ご飯を食べて、お風呂に入って、お気に入りのパジャマを着て自室に戻ると、変わらない両親の笑顔が出迎えてくれました。
「今日も楽しかったよ」
優しくて、歌が上手かったお母さん。
「ケーキは美味しかったし、クライヴのくれたチョコがとっても可愛いの」
強くて、いつも守ってくれたお父さん。
「わたし、明日も頑張るからね」
大好きな両親。
二人が残してくれたこの花屋を守りたくて、ずっと頑張ってきました。
それと、もう一つ。
思い出の中、幼き日の約束。
今も、今でも、忘れません。
わたしに、変わらない笑顔をくれたあの子のこと。
わたしの涙を優しく拭いてくれた小さな手と、ひまわりみたいな明るい笑顔。
セピア色の記憶。色彩は色あせても、この気持ちは変わらない。
もう何年も会ってないけど、元気でいますか。
この街のどこかで、笑っていますか?
「おやすみなさい」
わたしは、今日も笑顔でいます。
もう、『泣き虫めーちゃん』なんて言わせません。
あの時あの瞬間から、わたしは一度も涙を流していないのですから。
一人になってからも、花屋を開いてからも、ただの一度も。
あなたのくれた笑顔。
あなたと交わした約束。
今日も、わたしは守り続けています。
 Back Back
|