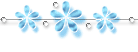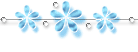|
* 一番好きな花 *
夢を見ます。
何度も何度も、同じ夢を。
楽しそうに笑う両親と、まだ幼かった自分。
花屋はいつもたくさんの笑顔で満ちていて、明るい笑い声が絶えることはありませんでした。
そんな当たり前の日常を、幸せだったと気付いたのは、全てがなくなってからでした。
わらっていてね、と。
わたしにそう言った、とても可愛い年下の女の子に、久しぶりに夢で会いました。
忘れたことは一度もないけれど。
記憶が薄れそうになったとき、あの子はいつも夢の中へ会いに来てくれます。
変わらない姿で。変わらない笑顔で。変わらない言葉を。
わらっているとたのしいよ。
まもってあげるから。だから、なかないで。
めーちゃんのわらってるとこ、だいすきなんだ。
でも一つだけ、いつもの夢とは違っていたことがあって。
あの子がいつも持っていたものが、そこにはなくて――
「っ!!」
飛び起きたという表現がぴったりなほど勢い良く起き上がったメレディスは、時計も確認せずベッドから降り、テーブルに置いてある、可愛らしい小物入れをそっと開けた。
「…………ふぅ」
安堵の溜息を漏らす。
ちゃんとあった。
夢の中でなくなったからといって、現実でもそれがなくなるはずがない。
そんなことは、考えなくてもわかることだ。
だが、その夢はあまりにもリアルで、鮮明で。
それが余計にメレディスを混乱させた。夢と現実の区別がつかなくなるほどに。
しかし、やはり夢は夢でしかなく。
ちゃんとそこにあった古びた袋を見て、メレディスはやっと笑顔を浮かべた。
「あれ……?」
ふと、窓の外を見やる。
随分と日が高い。
おかしいな、いつもと同じ時間のはず、と時計を見ると。
「――!!」
時刻は、もうすぐ正午になろうというところだった。
それからはもう、ものすごい速さで着替え、顔を洗い、朝食を食べ、開店準備に取り掛かった。
寝坊なんて滅多にしないのに、と、心の中で呟いた。
いや、メレディス本人も、原因は分かっているのだ。
あまりにも深い夢。
過去へ過去へと記憶が潜るほど眠りは深くなり、外界からの情報は全てシャットダウンされる。
今日は特にそれが強かった。一応セットしてある目覚まし時計の音さえも聞こえないほど、幸せだった頃の世界へ浸っていたかったのだ。
それほどまでに深い夢を見ることは滅多にないのだが、見ると必ず寝坊する。
そんな、『いつも通りではない一日』の始まりは、メレディスを密かに焦らせた。
もちろん、表情は常に笑顔なのだが。
それからも、何故かその日は『いつも通り』ではなかった。
ほぼ毎日立ち寄ってくれていたアルトマイヤーもベアトリスも、今日は忙しいのか、午後3時のティータイムになっても姿を見せなかった。
他にお茶に付き合ってくれそうな友人も来なかったので、この日、久しぶりに一人で紅茶を飲んだ。
客は普通に来ており、花を見繕ったり、業者へ依頼をしたりと、仕事の面ではいつも通りだったのだが。
僅かに感じる違和感だけは、なくなってくれなかった。
何度も何度も。
ふとした時に、昨日見た夢を思い出してしまうから。
両親の夢を見るのは割といつものことなのでいいのだが、その後に出てきた、小さな女の子のことが、頭から離れない。
あれから何年も経ったが、今でもはっきりと、あの時のことを思い出せる。
幼い頃、そこへ行くといつもその子が居て。
遊んだり、お喋りをしてして過ごした。
その子は自分に笑顔をくれて、大切な約束をした。
でも、もうそこへ行けなくなったから。
それから、その子には会っていない。
「……メレディスちゃん?」
「っ! あ、はい」
名を呼ばれ、メレディスは我に返った。
「ぼーっとしてたみたいだけど、大丈夫? 疲れてるの?」
「いいえ、そんなことないですよ」
会話中だったのに、つい夢のことを考えてしまい、ぼうっとしていたようだ。
話し相手になってくれていた近所のネコに心配される。
大丈夫だと、メレディスは笑顔で返した。
「お話の続き、聞かせてください」
優しい笑みを浮かべて促すと、そのネコは再び話し出した。
「そうそう、それでね、ケーキ屋に行ったんだけどね」
「はい」
「そしたら、すっごく大きな男の子が、一番人気のケーキを買ってたの。しかも5個」
近所のネコは、興奮した様子で言う。
男がケーキ屋に行くことは、メレディスからしたらさほど珍しくはないと思っているのだが。
「甘いものが好きなんでしょうか?」
「とてもそういう風には見えなかったけどね……。ガタイ良いし、マントであんま見えなかったけど、顔こわかったし」
「じゃあ、お土産かプレゼントかもしれないですね」
「ただのお使いとか。もしかしてパシリ。いやそんな馬鹿な……」
うーむと考え込む近所のネコ。
そんなにその大きな男の子がケーキ屋に居たことが不思議らしい。
彼女が言うように、よっぽど似つかわしくない見た目だったのだろうか。
しかしメレディスは、笑顔を崩さない。
「ふふ。きっとそのひとはいいひとなんです」
「顔こわかったよ?」
「見た目は関係ないですよー。だって、アルヤは甘いものがあまり好きではないし」
メレディスの言葉に、近所のネコは思い出したように言う。
「あ、アルヤちゃんね。こないだまた悪ガキに制裁加えてたよ」
「あらあら……」
「なんか、教会の子? がいじめられてたみたいで、駆けつけるなり縛り上げてたよ……ドS?」
「アルヤは弱いものいじめが大嫌いですから」
「うん。でも、実際その子がいじめられてたわけじゃなかったみたい。後ろに居た子を逃がしてたし」
「わ、偉いですね」
「いじめっ子を追い払って、実は迷子だったその子を教会まで送り届けてあげたみたいよ」
このネコはとてもお喋りで、色々な噂話や面白い話を知っているので、メレディスも楽しんでいた。
閉店までの僅かな時間を、そうして過ごした。
そして、辺りが暗くなり、【Mel Flower】の閉店時刻になった。
メレディスは、今日も楽しかったと心の中で呟いて、店のシャッターを下ろした。
いや、そう思い込みたかったのかもしれない。
夢の世界から抜け出せずに寝坊したことも、その夢のことばかり考えて過ごしていた今日の一日も、なんでもなかったことのように、これも日常の一つだと。
(……今日も、たのしかった)
この気持ちだけは、本当のことだけれど。
それでも、心は落ち着かなかった。
「……?」
店の裏、自宅へと続く玄関の前。
扉のすぐ前に、何かが置いてあるのが見えた。
「花……束?」
近付き、それを拾い上げる。
置いてあったものは、小さな花束だった。
紫色の美しい花が数本束ねられ、つたない結び方のリボンでラッピングされていた。
メレディスは、しばらくそれをぼうっと眺めていた。
何故なら、この花はメレディスが一番好きな花だったからだ。
アネモネ。
メレディスの瞳と同じ、紫色をした綺麗な花。
この色のものは珍しく、あまり見かけない上に、街の外にしか生えていないので、メレディスが手にする機会は、それほど多くなかった。
いったい誰からなのかと思考を巡らせる、が。
すぐに考えつく心当たりは一人しか居なかった。
メレディスに、わざわざ花をプレゼントしそうなネコといったら、幼馴染のクライヴェルグしか居なかった。
(……ううん。ちがう)
しかし、それは違うと、メレディスの本能が告げていた。
この花は彼からのものではない。
今まで彼から花をもらったことなど一度もないし、これからももらうことはないだろう。
だって、メレディスは『花屋』なのだ。
花屋に花をプレゼントなんて、彼がするはずがない。
ならば、誰が?
考えても答えは出なかった。
メレディスの知り得ない、どこかの誰かからの贈り物。
手紙などはついていないし、もちろん差出人の名前も、どこにも書かれていなかった。
「……」
誰が置いてくれたのか、どういう意図なのか、そんなことは、メレディスにはどうでもよかった。
この花にあるのは、繊細な美しさと、贈り主がこめた想いだけ。
きっと、贈り主はとても花が好きなのだろう。つたないリボンは、きっとこういう渡し方に慣れていないから。
(綺麗だなぁ)
それでも、自分を想って結んでくれたものだ。
メレディスは店に居たのに、わざわざ裏口に置いたのには、なにか理由があったんだろう。
恥ずかしかったのか、それとも、どう言って渡せばいいのか分からなかったのか。
そう考えると、自然と表情が笑顔になった。
「……ありがとう、ございます」
そして口から出てきたのは、お礼の言葉。
周りには誰も居ない。
でも、言わずにはいられなかった。
嬉しかった。
ただ、嬉しかった。
花屋を開いてから、花をもらったことは一度もなかった。
花が大好きなのに。花屋をやっているから、花を贈られることはなかった。
そんな自分の、小さな悩みを見透かされたようで。
『あなたは花が好きなんだよね』と語りかけられたようで。
メレディスは、微笑みながら、胸元へとアネモネを抱き込んだ。
「……?」
それと同時に感じる違和感。
アネモネのものではない香りが、メレディスの鼻をくすぐった。
それは、花を包んでいる包装紙からだった。
鼻を近づけると、それからは薬のような匂いがした。独特な、薬草の匂いとでも言うのだろうか。
ということは、このアネモネの贈り主は、薬屋でもやっているのだろうか。
メレディスは「もしかしたら」と思考を巡らせようとして、やめた。
贈り主の正体より、今この手の中にある花の美しさの方が大切だし、きっと直接渡さないのには理由がある。
これ以上自分の中で真実を追求しても、答えは出ないのだから、と。
そうして、無理矢理思考を止めた。
メレディスは自室へ入ると、ちょうど空いていた小さな花瓶へ花を活けた。
柔らかく微笑むと、もう一度、心の中でお礼を言った。
お母さん、お父さん。
今日、花屋を開いてから、初めてお花をもらいました。
とっても綺麗な、紫のアネモネ。
子供の頃からの、わたしが一番好きな花です。
誰がくれたのか分かりませんが、怖くなんてありません。
だって、お花が好きなひとに、悪いひとは居ない。
お母さんは、いつもわたしにそう言ってくれましたね。
お父さんもお花が大好きだって。お母さんはお花みたいとも言っていましたね。
「ふふ、可愛い」
この花を見ていると、どうしてか、あの子のことを思い出します。
不意に贈られた花束は、あの時、突然わたしの目の前に現れた、小さな女の子を連想させて。
嬉しくて、楽しくて。
いつの間にか日常に溶け込んでいたあの頃の日々のようで。
贈り主の分からない花束も、何の抵抗もなく受け入れることができる。
あれからもう何年も経ったけれど、わたしは、やっぱりあの子に会いたい。
でも、会いに行く勇気がないから。
あの場所に行く勇気が、今のわたしにはないから。
だから。
紫のアネモネの花言葉は、たしか。
――『あなたを信じて待つ』。
……わたしは、今も待っています。
あなたが、ここへ迎えに来てくれるのを。
遠い日の約束を、果たしてくれるのを。
信じて……待っています。
 Back Back
|