 |
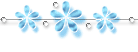 |
 |
|
* 淡い期待 *
わたしの元へ、差出人が不明のアネモネが贈られてから三日後。 また、裏口へ花束が置かれていました。 差出人は、やっぱり不明で。 リボンも、やっぱりぎこちなくて。 包み紙から香る薬の香りも、同じでした。 その花は本当に美しくて、生き生きとしていて。 街の外で取れる花は、こんなにも綺麗なんだと思いました。 生まれてこの方、街の外へ出たことがないわたしが知らないものを、この贈り主さんは知っているのが、羨ましくなりました。 このひとは、わたしよりたくさんのものを知っている。 わたしには分からない外の空気を知っている。 それがとても羨ましくて。 いつか、自分の足で、外の世界を見に行けたらいいな……と。 そんなことを、考えました。 それからも、数日置きに花は置かれていました。 決まって裏口に。 必ず夕方に。 暗くなるまでの、そう長くない間。わたしが店を閉めて自室へ戻るまでの時間に。 わたしのよく知っている花や、見たことのない花、珍しい花……いろいろな花が。 最初のうちは数日置きに。それから少し空いて、まちまちに。 三ヶ月ほど経った頃には、一週間に一度、置かれるようになりました。 そんな日々の、色々な出来事のお話。 ――ある日はスイートピー。花びらがひらひらと可愛らしく甘い香りのする花。 置かれていた花を拾い上げると香るスイートピーの香り。 ピンク色で、とっても可愛くて、眺めていると笑顔になれます。 ――花言葉は『優しい思い出』。 * * * * * 「メレ」 「あ、アルヤ。いらっしゃい」 いつもより遅い時間にやってきたアルトマイヤー。 表情はやや暗く、声音にもいつものような元気はなかった。 メレディスが違和感を感じ椅子から立ち上がり声をかけると。 「……アルヤ、怪我したの?」 「不覚だったのだわ」 片腕を押さえていたアルトマイヤーが、力なく言った。 見れば、彼女の両腕を常に覆っているアームウォーマーが破れて、隠されていた腕があらわになっていた。 そして、わずかにだが血が滲んでいるのが見えた。 「待ってね、すぐに手当てするから」 「……うん」 店に客は一人も居なかったので、メレディスは店の奥へ入り、小さな救急箱を持って戻ってきた。 アルトマイヤーは、いつもお茶会をする時に使っているテーブルに歩み寄り、しゅるしゅると、アームウォーマーの紐を解きながら腰を下ろした。 「痛い?」 「ちょっとだけ」 傷口に当たらないように、そっとそれを外すと、隠れていた傷が顕になる。 血は、既に止まっている。 何かの爪で引っかかれたような切り傷。メレディスは、清潔な濡れタオルで優しく血を拭いた。 「……」 口元に、穏やかな、慈愛にあふれた笑みを浮かべ、アルトマイヤーの手を握りながら、メレディスは無言で手当てをする。 そんなメレディスを、アルトマイヤーは少しだけ遠い眼差しで見つめた。 アルトマイヤーの腕には、生々しい切り傷だけではなく、もう治ってはいるが痕の消えない傷、火傷の痕が刻まれている。 彼女がいつも腕を隠しているのは、その傷跡を見せたくないからだ。 ただ包帯を巻くだけでもいいのだが、そうすると周りに与える印象が悪くなると考えていた。 お世辞にも綺麗とはいえない己の腕を、彼女は嫌悪していた。 なぜなら、その傷をつけたのは、彼女の両親なのだから。 「できたよ。これで大丈夫」 「ありがと、メレ」 ここで、やっとアルトマイヤーが笑顔を見せた。 彼女の傷のことを知っているのは、幼馴染であるメレディスと、ベアトリス、クライヴェルグだけだった。 だから、腕に怪我をした場合……大抵は自分で手当てをするのだが、時間のあるとき、アルトマイヤーはいつもメレディスの元へ来る。メレディスに触れられていると落ち着くし、傷の痛みも、知らないうちになくなっているから。 「それも直してあげるね。裁縫道具も持ってきたから」 「う、うん。助かるのだわ」 言うと、アームウォーマーの破れてしまった部分を、器用に縫い合わせた。 アルトマイヤーは、料理はできるのだが、裁縫は苦手だった。 やってみようとして指に針を刺してしまったことは数知れず、マフラーを編もうとしたらよくわからない物体になったりと、そういった方面ではとにかく不器用だった。 それから、閉店時間になるまで、アルトマイヤーとのんびり過ごした。 別れ際、『今度は美味しいものを作って持って来るのだわ』と笑顔で言い残し、ギルドネコの宿舎へと帰って行った。 * * * * * アルヤがこうしてわたしに手当てしてもらいに来るのは、もう何度目でしょうか。 本当は、腕の傷跡を見るだけで心が痛みます。 幼い頃のアルヤは、今よりずっと小さくて、か弱くて、いつも涙をこらえていて。 わたしより少しだけ年上ですが、姉のように慕ってくれるアルヤが、わたしは大好きです。 作ってくれる料理はどれも美味しいものばかりですし、わたしが作るお菓子も、いつも喜んで食べてくれます。 そういえば、ずっと昔にも、似たような思い出がありました。立場は逆でしたけれど。 わたしと約束を交わした小さな女の子。 遊んでいる途中、わたしが石に躓いて転んでしまったとき、つたない手つきで薬を塗って、手当てしてくれたあの子。 あの子の塗ってくれた薬はとてもよく効いて、ちょっと痛かったけど、怪我はすぐに治って。 最後は必ず笑顔をくれました。 そんな、優しい思い出。 ――またある日はシンビジウム。小さく上品な花が何輪も咲いている、ラン科の花。 白い花がとても綺麗で、日光がよく当たるよう、自室の窓際に飾りました。 陽の光を浴びた花がどこか神々しく見えて、久しぶりに歌いたくなりました。 ――花言葉は『飾らない心』。 * * * * * その日はよく晴れていて、気温もいつもより高く、メレディスは大切な花たちが弱らないよう、いつもより念入りに世話をした。 外に出していたものが少し元気がなさそうだったので、室内に置き、肥料を与えた。 元気になってね、と。 穏やかな表情で花に語りかけるメレディスの様子を、静かに眺める姿があった。 「こんにちは、メレ」 ベアトリスだ。 いつものようにギルド帽子をしっかりかぶっていて、片手には愛用の厚い本、もう片手にはバスケットを持っていた。 「トリス、いらっしゃい」 メレディスは笑顔で立ち上がり、エプロンをほどきながらベアトリスの元へ歩み寄った。 ランチタイムにベアトリスが花屋へ来るときは、大抵何か持ってきてくれている。 「今日はサンドイッチなの。一緒に食べましょう」 「うん。ありがとう♪ サラダ持って来るね」 アルトマイヤーほどではないが、ベアトリスも多少は料理ができる。簡単なものがほとんどだが、こうして時たまメレディスと食事を摂るためにやってくるのだ。 壊滅的に料理ができない(サラダくらいならなんとか)メレディスを気遣っているのがひとつ。 それと、一人で店を頑張っているメレディスのそばに、できるだけ居てあげたいという気持ちからだった。 サンドイッチを頬張りながら、何気ない会話を楽しむ。 この時間は昼休憩なので、店の前には休憩中の立て看板が置いてある。 美味しそうに食べるメレディスの笑顔を見て、ベアトリスも静かに微笑む。 メレディスは今日も変わりなく元気で、笑って過ごしていることを嬉しく思うのだ。 「あら? いつもと違う香りがするわね」 お茶のおかわりを、ベアトリスのそばで注いでいたところ、不意にかけられた言葉。 メレディスは疑問の表情を浮かべたが、すぐに理由がわかったようで、 「ふふっ、そうかも」 嬉しそうな微笑で返した。 今度はベアトリスが怪訝そうな表情になる。 「何かあったの?」 「珍しい花を自室に飾ってるから、その香りだと思うよ」 「そうなの。メレはいつもいい香りがするから、一緒に居てとても安らぐわ」 普段はあまり見せない、ベアトリスの穏やかな笑顔。 「それにとても可愛らしいし、変な虫がつかないかいつも心配なのよ。……まあ、私とアルヤのガードは鉄壁だけれど」 「えっ?」 「なんでもないわ」 彼女は、近しい相手には、思うままの言葉を伝えるのが常だった。 美しいものを美しいと言い、好きなものは好きと言う。 悪事は決して見逃さないし、大切な者を守るためならば攻撃的な手段に出ることもある。 「大好きよ、メレ」 「……ありがと。わたしも、トリスが大好き」 少しだけ頬を赤らめて、笑顔で返した。 いつも自分に優しくしてくれて、暇のあるときはいつも会いにきてくれる親友が、メレディスは本当に大好きで、大切だった。 「色々してもらってばっかりだね」とメレディスが言えば、「親友なんだから当たり前よ」と返って来る。 もちろん、その気持ちに応えたいと、ティータイムに自作のお菓子を用意したり、美味しい紅茶を用意したりもしているのだが。 やはり、そばに居てくれることが一番嬉しいから。 だから、当たり前だと言われても、感謝の気持ちはいつも忘れない。 * * * * * そういえば。 あの子も、トリスみたいに、いつも自分の思うことをストレートに伝えてくれていました。 「めーちゃんはかわいいね」 「おうたがじょうずだね」 「ないてると、かなしい。なかないで」 わたしの方が年上だったのに、わたしはいつも泣いてばかりで。 あの子の……飾らない、心のままの言葉に、何度も救われました。 でも、わたしは、そんなあの子に「ありがとう」しか伝えられなくて。 いつも、明るい笑顔と元気をくれていたのに。 今のわたしは、あの子にもらった笑顔を忘れないことで精一杯で。 飾らない言葉を口にすることが、ほとんどないということに気付いてしまいました。 涙は流してないけれど。 ちゃんと笑えているけれど。 ……やっぱり、あの子に会いたいです。 ――しばらく後にクラスペディア。黄色い花が集まり咲いた、まんまるの花。 主に切花やドライフラワーなどに使う花で、その独特の形から、花壇に植えても目立ちます。 ――花言葉は『心の扉をたたく』。 * * * * * 『来週、一緒に食事に行こう。迎えに来るから』 それだけをメレディスに伝え、足早に帰って行ったクライヴェルグ。 詳しい時間、場所などは知らされず、ただ約束だけを取り付ける。 普通なら色々と不安になるところだが、何度か出かけたことのあるメレディスは、特に気にする様子も見せずに承諾した。 いつクライヴェルグが来てもいいようにと、あらかじめ出かける支度をしておく。 といっても、これといって用意するものはないのだが。 そして夕方。暗くなるにはまだ少し早い頃。 いつもと全く変わらない装い――つまりは軍服なのだが――のクライヴェルグがやって来た。 もちろん手土産を持って。 「わ、いつもごめんね」 「気にするな。オレがあげたいからあげるんだ」 「……ふふ、そっか」 穏やかな微笑を浮かべると、クライヴェルグはやや目を逸らし、開けてくれないか、と小声で言った。 メレディスはそれに頷き、包みをほどく。 中には、星を模った小さなヘアピンが入っていた。光が当たると、きらりと星が色を変える。 「かわいい〜♪」 「たまには、こういうのもいいだろ?」 「うん、ありがとう」 「……ああ」 にこにこ笑いながら、もらったヘアピンを早速髪につけてみるメレディス。 「どうかな」 ヘアピンがクライヴェルグによく見えるように、少しだけ横を向いた。 「…………似合うよ」 かなりの沈黙のあと、小さな声でぽつりと言う。 恥ずかしいのか、視線を合わせずに。 その言葉を聞いたメレディスは、嬉しそうに笑った。 あまり口数の多くないクライヴェルグだが、彼の優しさは、ちゃんとメレディスに伝わっている。今はそれほどでもないが、幼い頃から一緒に過ごしてきたの だ。些細な挙動や言葉でも、相手を思いやっていることがうかがえる。そのくらい、メレディスはクライヴェルグのことを解っているのだ。 食事は、メレディスの家から少し離れた所、街の北あたりに位置するレストランですることになっていた。 二人ともその店には行った事がなく、クライヴェルグ曰く『肉が美味い』。同僚に勧められた店で、美味い店なら連れて行きたいと思ったんだと、道すがら話した。 しばらく後、食事を終えたメレディスとクライヴェルグが店を出てきた。辺りは既に暗く、魔法によって灯された街灯が淡く道を照らしていた。 料理は美味だったのだが、一人前の量がかなり多く、味付けもどちらかといえば粗野で、お世辞にもデートで行くような店ではなかったと、普通の人なら思うものだった。そもそもデートコースとして勧められた店ではなかったから、当然といえば当然なのだが。 しかし、クライヴェルグはあまりそういうことを深く考えるタイプではなく、料理が美味しければいい、という結論にいつも至る。メレディスが食べ切れなかった分を分けてもらって、結果的にかなりの量を食べることになったが、顔色一つ変えずに完食した。 「美味しかったねー」 「そうだな」 そしてメレディスも、同じようにそういった方面に疎く、美味しいご飯を食べられて満足という印象しか抱いていなかった。 一人で喫茶店やケーキ屋に行くことはあっても、外食は滅多にせず、こうしてたまにクライヴェルグに誘われて行くくらいだ。普段食べないようなものを食べられたら嬉しくもなる。好き嫌いはあまりないので、誘われたらどこへでも行った。 アルトマイヤーが作ってくれる料理は、ほとんどが家庭料理で、華やかではなくどちらかといえば質素だが、味は確かだった。日頃の自炊の賜物だ。メレディスが壊滅的なまでに料理下手なせいで、アルトマイヤーの料理は月日を追うごとに上達していく。 と、メレディスが何気なく横を見ると、もうとっくに閉店しているが、一軒の花屋が目に入った。 メレディスの店とは違い、落ち着いた外装で、シックな色合いの看板だった。 「そういえばね」 「ん?」 メレディスは、花屋を見て思い出したことがあった。 最近、たびたび贈られている差出人不明の花のことだ。 なんてことのない世間話のつもりで話し出す。 「最近、店を閉めたあと、裏口に花が置かれているの」 メレディスの言葉に、クライヴェルグの表情が少しだけ変わった。 かすかな驚きから、不安そうなものへ。 「……花?」 「うん。街の外でしか取れないような……っくしゅん」 小さなくしゃみ。昼はとても暖かい世界なのだが、夜はやや冷え込み、冷たい風が吹く。 いつも羽織っているケープではなく、薄手のボレロを着てきたメレディス。 普段、暗くなってから外出することがあまりないので、どの上着を着ていくべきか迷い、手ごろなものにした結果、少し肌寒くなってしまった。 そして、まだ彼女の花屋までは早く歩いても時間がかかる。 「大丈夫か? ほら、着てろ」 クライヴェルグが、軍服の上に纏っていた外套を脱ぎ、そっとメレディスの肩にかけた。これだけでもだいぶ暖かくなるだろう。 彼の外套はギルドからの支給品で、もう長年使い古されたそれは、裾の部分がややほつれたりしていた。クライヴェルグ本人は特に気にした様子もなくいつもそれを着ているが、ギルドの仲間からは不評だった。 メレディスはやはり気にしていなかったが。ちなみに、長身の彼に合わせたサイズなので、メレディスが羽織るとだいぶ長い。地面につきそうなほどだ。 「あ、ありがとう」 嬉しそうに、にっこり笑うメレディスと、ほっとしたような笑みを浮かべるクライヴェルグ。 とその時、 「あら? メレじゃない」 「クライヴもいるのだわ」 背後から、ベアトリスとアルトマイヤーが声をかけてきた。 もう勤務時間ではないので、二人とも帽子を外している。 「ふたりとも、お疲れ様ー」 笑顔で手を振りながら、二人のもとへと歩いていくメレディス。クライヴェルグは無言でその後に続いた。 メレディスの羽織るクライヴェルグの外套と、髪に光るヘアピンを見て、 「デートかしら」 「デートね」 アルトマイヤーとベアトリスが、面白くなさそうな顔で言う。 クライヴェルグはばつが悪そうに、 「……食事だ」 と短く返した。 内心、この二人にはあまり見つかりたくなかった。 今はいいのだが、後日一人で居るときに会ったら、何を言われるか恐ろしいからだ。 幼馴染だからそれほど警戒されてはいないのだが、もし手を出そうものなら八つ裂きにされるかもしれないという恐怖を彼は抱いていた。 アルトマイヤーとベアトリスは、メレディスに対してはいきすぎるまでに過保護だから。 二人はこれから宿舎に帰る途中で、どうせ時間もあるからと、メレディスを家まで送るのに同行することになった。 メレディスは、花の話を再開する。 「それでね、最近、よく花をもらうの」 「花ねぇ。でも誰からかわからないのでしょう?」 「うん。いつも裏口に置いてあって、何も書いてないの」 「ちょっと心配になるわね。……何もなければいいのだけど」 贈り主不明の花束は、やはり幼馴染たちの不安をあおり、二人は、メレディスを心配そうな眼差しで見やった。 しかし当のメレディスは何も気にしている様子はなく、いつもと同じ笑顔を浮かべている。 「大丈夫だよー」 「随分落ち着いているのだわ……メレっぽいけど」 「だって、花が好きなひとに悪いひとはいないもん」 「メレの気持ちはわかるわ。悪意はなさそうだし」 と、クライヴェルグが思い出したように顔を上げた。 彼は、四人で居るときは何故かあまり喋らない。アルトマイヤーとベアトリスと、楽しそうに話すメレディスの姿を見て、たまに相槌を返す程度だ。 「……そういえば、数ヶ月前、初対面のヤツから花をもらった」 その言葉に、アルトマイヤーとベアトリスがはっとする。 「あたしも」 「私ももらったわ。多分、同じ日じゃないかしら」 これにはメレディスも驚き、 「え? みんな、同じひとにもらったの?」 と、三人の顔をそれぞれ見た。ぱちぱちとまばたきを繰り返す。 「あー、なんか、でかくて」 「赤い短髪で、目は金色で」 「顔こわかったのだわ」 自分の言いたかったことが、それぞれ一つずつ言われた三人は顔を見合わせた。 少々の沈黙の後、アルトマイヤーが軽く溜息を吐いた。 「まぁ、メレに花を贈っているひとと同一人物とは限らないのだわ」 「そうね。全くの別人かもしれないし」 確かにその通りだ。三人に花を渡したのが同一人物でも、それとメレディスへの花とは別問題。 なので、メレディスはあまり深く気にせず、『そのひとも花が好きなんだろう』という考えにしか至らなかった。 先日、友人がケーキ屋で見かけたネコの話と一致する要素があるので、きっとそのひとなんだろうと思いながら。 「きっとそのネコは、メレのことが好きなのだわ。ラブなのだわ」 クライヴェルグの眉がぴくりと動いた。 「貴女は本当にそういう話が好きね」 「だって面白いのだわ」 ベアトリスが呆れたように言って、アルトマイヤーが悪戯っぽく笑う。しかしメレディスは落ち着いた様子だ。 「そうかな。案外、花が好きそうだからって理由かもしれないよ。珍しい花ばかりだもん」 「甘いのだわ。普通、花屋に花なんて贈らないのだわ。珍しいからって、絶対手に入らないわけじゃないし。その花に自分の気持ちを込めに込めまくってるに違いないのだわ。直接渡さないのは……照れ屋なのかしら」 「うーん……」 アルトマイヤーが興奮した様子でまくし立てる。 いつもこの手の話には興味津々で、すぐに乗ってくる。『面白そう』という理由でだが。 「でも少し弱いわね。カードか何かあればいいのに」 「いきなり現れてプロポーズとかしてくるかもしれないのだわ」 「は、話が飛躍しすぎだよー」 そんな三人のやりとりを、クライヴェルグは神妙な面持ちで聞いていた。 花の贈り主が気になるのか、ぐるぐると思考を巡らせている。二人の話をかなり真に受けており、表情はどんどん厳しくなっていった。 「……まぁ、あたしたちのガードは鉄壁なのだわ。易々とメレを渡してたまるもんですか」 「ふふ、そうね。変な輩だったら困るものね」 黒い笑みを浮かべるアルトマイヤーとベアトリス。 メレディスに異性の影がほとんどないのは、実はこの二人が陰ながら色々やっているからという噂もある。 「……張る?」 「……張るわ」 何を?と思いつつも、メレディスは苦笑いのまま。クライヴェルグは、いつの間にか無表情に戻っていた。 結局花の贈り主の話はここで終わり、あとは世間話をして、メレディスの家まで歩いた。 ギルドの宿舎へ帰っていく三人を笑顔で見送り、裏口へと回ると。 少しだけ元気のなさそうなクラスペディアが、静かに待っていた。 「……!」 結構な時間が経ってしまっている。強い花だから大丈夫だろうが、メレディスは、慌てて拾い上げ、家へ入っていった。 * * * * * 今日は、久しぶりに四人で話せて、とても楽しかったです。 みんなと話して、この花の贈り主のことが、少し気になってきました。 どこの誰なんでしょうか。 やっぱり、アルヤたちが言っていたひとなんでしょうか。 それとも、全く違う誰か? でも、きっととても花が好きに違いありません。 花が好きな、優しい心を持ったひと。 わたしは、そう思います。 贈られ続けている花は、どの花も、わたしの心の扉を、小さく叩きます。 気付いて欲しい。 この花に込められた想いを知って欲しい。 まるで、そう、花が言っているかのようで。 次はどんな花が贈られるのだろうと、わたしは少しずつ思うようになりました。 いつの間にか、その”誰か"のくれる花束が楽しみになっていたのです。 わたしに笑顔をくれる花たちは、まるであの子のよう。 何も言わずに会えなくなった、幼い頃の心残り。 そう、もしも贈り主があの子なら――。 ――そして、数ヶ月が過ぎたある日のスターチス。紫色の小さな花の中に、更に小さな白い花を咲かせる、美しい花。 この花を見た瞬間、わたしの心は、一瞬で過去へと返ったかのように、あの子の笑顔が、はっきりと脳裏に浮かびました。 あと、もう一つ……あの子の涙も。 わたしの涙につられるようにあの子も泣き出して。どちらが慰めているのかわからなくなって。 大好きだよって。 ずっと一緒に居るって。 子供ながらに信じていました。 大切な、大切なお友達。 わたしより幼くて、小さくて、体も弱かったのに、いつも『守ってあげるから』と言ってくれていたあの子。 本当は、お姉さんであるわたしがあの子を守らないといけなかったのに。 あの子の言葉が嬉しくて、信じたくて、だから、このままずっと一緒に居るんだって思っていて――。 でもそれが、ある日突然叶わなくなりました。 些細なことから引き起こされた重大なことで、ふたりの心はすれ違ったまま、離れ離れ。 気付けば何年も過ぎていて……。 会いたいと思っているのはわたしだけなんじゃないのかって、たまに思ったりもして。 自分から会いに行ったほうがいいんじゃないのか、ちゃんと花屋を開いたことを知らないんじゃないのかなんて、不安になったりもしました。 でも、信じているから。 何年も経った、今この時も。 あの子がわたしを覚えていてくれて、迎えに来てくれるのを信じているから、わたしは待っています。 だって、それがふたりの約束だから。 この花を見て、わたしの中に、ある一つの思いが芽生えました。 ――スターチスの花言葉……『私の心は永遠に変わらない』。 贈り主が、あの子だったらいいのにと――。 * * * * * 「めぇちゃん、だいすき」 「わたしも、みーちゃんがだいすき」 「みぃ、ずっといっしょにいるからね」 「うん。いっしょだよ」 「やくそくっ」 「やくそくー」 「ねぇ、おうたうたって?」 「いいよー。みーちゃんもいっしょにうたおう?」 「うん!」 遠い日の約束。 忘れることのない思い出。 重なる手と手。 そして――歌声が、ひとつになる。 |
||
 |
 |
 Back
Back