 |
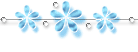 |
 |
|
* 花の贈り主 *
花が贈られるようになって、もうすぐ四ヶ月になろうとしていました。 季節は少しずつ移り変わり、日中は、少し暑く感じます。 一週間に一度、定期的に置かれるようになった花たち。 裏口に置かれる花を見る度に、わたしの心は明るくなり、まだ見ぬ贈り主に思いを馳せる日々が続きました。 あの子なら、みーちゃんなら、一刻も早く会いたいと。 今、どんな姿をしているのか。どんな顔で笑うのか、どんな言葉をくれるのか。 知らず知らずのうちに、期待ばかりが膨らんでいました。確かな証拠なんて、どこにもありはしないのに。 ただ、そうだったらいいな、と。 思うことは、止められなくて。 でも、最近は、そうじゃないのかもと思うことの方が、ずっと多くなりました。 なぜなら――。 「……?」 ここ一月ほど、働いていると、どこからか視線を感じることがよくありました。 すぐ近くから見られているような。じっと見つめられているような。 気になって、視線を感じる度に振り向いても、そこには誰も居ません。 いいえ、居たのかもしれませんが、その姿を視界に収めることはできませんでした。 そういえば、みーちゃんはちょっぴり恥ずかしがりやさんだったなぁと思い出して、顔を合わせるのが照れくさいのかな、なんて思ったりしました。 けれど……。 「――!」 最近、知らないひとと、目が合うことがよくあります。 少し距離があるので、どんな顔をしているのかはよく分からないのですが。 いつも同じ、店の反対側、斜め奥の曲がり角から、少しだけ顔を出して、わたしの方を向いているのです。 そして、目が合った瞬間、姿を引っ込めてしまいます。 だから、誰なのかは分からなくて。でも、きっと知らないひと。 ほんの一瞬で分かるのは、背がとても大きいということと、いつも長い外套で顔を覆っているということだけ。 それから気付いたこと。 そのひとと目が合った日は、必ず花が置かれているのです。 摘んでからそれほど時間の経っていない、元気で、綺麗な花が。 あのひとが、わたしに花を贈り続けてくれているのでしょうか。 やっぱり、みーちゃんじゃないのでしょうか。 みーちゃんじゃないとしたら、あのひとが贈り主だとしたら、いったいなぜ、わたしに花を贈るのでしょうか。 わたしの知る限り、あんなに背の大きな男性は、周りに居なくて。 目を合わせてもすぐに居なくなってしまうあのひとは、何を思っているのでしょう。 アルヤたちの言っていたように。 茶飲み友達が言っていたように。 お花が好きで、甘いものが好きで、初対面の相手にも花を贈れる優しさを持っている、そんなひとなら。 わたしは、お友達になりたい。 そんなことを、考えました。 声が聞こえた。 それは小さな叫び声で、いつも視線を感じる曲がり角から。 外に居たメレディスが声のした方へ振り返ると、長い長い外套が、石の柵に引っかかっているのが見えた。 それを見た瞬間、彼女は走り出した。 助けてあげなければと思ったのが一つ。 花の贈り主かもと思ったのが一つ。 あわよくばお話ができたらと、そんな気持ちがほんの少し。 「あの、大丈夫ですか?」 「……!」 駆け寄り、傍らでしゃがみこむと、引っかかった外套をそっと外した。 それと同時に、もうすっかり嗅ぎ慣れた薬のにおいがした。 いつも、花束を包んである紙と全く同じだった。間違うはずがなかった。 メレディスは確信した。 贈り主はこのひとだ、と。 ほんの一瞬だが、顔を上げるのを躊躇った。 『みーちゃん』じゃないことは、もう、この大きな体躯を見たときから分かっていた。 だってあの子は可憐な女の子だったのだ。 だからこのひとは、メレディスには何の関わりもなかったということになる。 「…………」 立ち上がり、ゆっくりと、顔を上げた。 相手の顔は思っていたよりずっと高い位置にあって、身長差がかなりあることを感じさせた。 視線が交わる。 くすんだ赤い髪の毛と、先がくるんと丸みを帯びた耳、頬には朱色の紋様。そして、珍しいとされる金色の瞳。 その表情は、驚きと戸惑いが同居していて、寄せられた眉根は、一見しただけでは怖いという印象しか与えない。 しかし、メレディスの心情は違ったものだった。 親友から聞く通りの人物ならば、花が好きで心優しい青年なのだろう。 それならば、どんなに見た目が怖くとも、きっと悪いひとではないと。 だから、勇気を出して。 「あの、」 「!」 声をかけてみたのはいいのだが、相手はどこか挙動不審で、一筋の汗が頬を伝うのが見えた。 それから、ゆっくり、ゆっくりと後ずさったかと思えば、声も上げずに立ち去ってしまった。 「……?」 どうしたのだろうと首を傾げる。 と、 「……あ」 相手が振り向いたときに落ちた袋が、道に残されていた。 歩み寄り、拾い上げる。 薬袋だった。 見れば、店名らしき文字が印字されている。 『ルクリス』と。 「――!!」 その名前には聞き覚えがあった。 幼い頃、何度も母と通った薬屋だった。 メレディスが『行く勇気が出ない』と、敬遠している場所でもあった。 その場所は、『みーちゃん』と出会った場所であり。 『みーちゃん』と言葉を交わさぬまま別れた場所でもあったから。 メレディスは、昔の記憶を必死に呼び起こす。 『みーちゃん』は小さく可憐な女の子で、そうだ、確か兄が居ると言っていた。 名前を聞いたことはなかったが……そもそも、本人ですら自分のことを『みぃ』としか言えなかった。メレディスは、『みぃ』ちゃん。から、みーちゃん。と呼んでいただけに過ぎない。だから、本当はもっと違う名前のはずだと。 しかし、子供心とは単純なもので、相手の名前がわからなくとも、一緒に遊んでいて楽しければ、それでいいのである。 そして、その兄には、メレディスは会った事がなかった。 その店で心当たりがあるとするなら、みーちゃんの兄だが、そもそも会ったことがないのに花を贈られる理由が分からない。それも、こんな唐突に。 メレディスの知る限り、あの店には、『ルクリス』には、他には二人の両親しか居ないのだから。 贈り主が結局誰だったのか分からないまま、メレディスは店へと歩き戻った。 どうして逃げるように立ち去ってしまったのか。 どうして何も言ってくれなかったのか。 考えても考えても、答えは出なかった。 それから数時間が経った後。 花屋の昼休憩の時間になった。 いつものように『休憩中』の立て看板を設置していると、視界に長い外套が目に入った。 その方向を見やると、花の贈り主が険しい表情で右往左往していた。手に、花束と菓子折りを持って。 そして、目が合った。 メレディスは柔らかく微笑むと、 「こんにちは」 優しく声をかけた。 相手が、何も言わず立ち去ってしまったことを気に病んでいるかもしれないと思ったメレディスは、『気にしていないから大丈夫』ということが伝わるよう、いつもよりずっと優しい微笑を浮かべた。 「こ……こん、にちは」 返事があった。 それはかなり低い声で、かなりしどろもどろだった。 緊張しているのかなとメレディスは思い、相手にゆっくり歩み寄ると、ぺこりと頭を下げた。 「はじめまして。わたし、メレディスっていいます」 「……はじめまして。――朝、礼も言わず……すまない」 言うと、手に持った花束――橙色の、鈴蘭のような花――を、そっと差し出した。 「ミキ。――……南地区の裏、薬屋」 「!」 初めて、直接渡される花束に、メレディスは驚いた。 だが、それ以上に嬉しさの方がずっと多かった。 四ヶ月もの間花を贈り続けてくれていたひとが、今目の前に居て、そしてまた花束を、今度は直接、自分に贈ってくれているのだ。 メレディスは、自分でもよく分からない気持ちを覚えながら、差し出された鈴蘭に似た花を受け取った。本物とは少し形や色が違っている花(鈴蘭より花が小ぶりだった)で、メレディスにもその花の正式な名前は分からなかった。 「ありがとうございます。やっぱり、あなただったんですね」 「……いつも、あな……花、……綺麗だと思って……」 「そうですね、綺麗なお花です」 にこりと微笑む。メレディスの笑顔に、ミキの表情もいくらか和らいだ。 「これも。……朝の、詫び」 「えっ……? わ、ありがとうございます」 菓子折りを差し出された。 お詫びをされるほど失礼なことをされたとは思えず、とりあえず受け取るが、それはけっこうな量があった。 香ばしい匂いがかすかにするので、中身は焼き菓子だろう。 こんなにたくさんどうしよう……と考えるが、そういえば今は昼休憩の時間だ。 メレディスはあることを思いつく。 「もしよろしければ、お茶していきませんか?」 「……え」 ミキの表情が固まる。 そんなことを言われるとは思っていなかったのか、「え、あ、あの、でも、だって」と、言葉が途切れ途切れになっていた。 「お話したいんです……だめ、ですか?」 困った表情でミキを見上げると、ミキは言葉に詰まった様子で、眉根を寄せ、ぶんぶんと首を横に振った。外套に隠れているので、表情の変化は窺えなかった。 メレディスの表情がぱあっと明るくなる。 「今、お店の休憩時間なんです。どうぞお入りください」 促すと、ミキは無言で頷いて、メレディスに続いて店に入った。 店の中にある、いつも友人たちとお茶を飲むテーブルに菓子折りを置いて、もらった花は、手近な花瓶に挿した。 「お茶を淹れてきます。紅茶はお好きですか?」 「……」 ミキはこくんと頷いた。 「ふふっ、では、少々お待ちくださいね」 自分の中でもかなりお気に入りの茶葉を選び、紅茶を淹れる。 そういえば昼食を摂っていないが、夜にちゃんと食べればいいだろうと思い、トレイにティーポットと、二人分のティーカップ、小皿を載せ、ミキの待つテーブルへと戻った。ミルクとシュガーはテーブルに常備してある。メレディスはストレート派だが。 「お待たせしました」 戻ると、ミキが菓子折りの包みを開封してくれていた。 中身はスコーンで、綺麗な焼き色と、小麦の豊かな香りが食欲をそそる。シンプルながらも飽きの来ない焼き菓子だ。 「……ありがとう」 じっくり蒸らした紅茶をカップに注ぐと、茶葉のいい香りが漂った。 小皿を置くと、ミキが「どうぞ」とスコーンを載せてくれた。メレディスはお礼を言って、紅茶をミキの前へ置いた。 と、 「あっ」 「?」 メレディスが、ぽんと両手を叩く。ミキが首を傾げる。 「スコーンにはジャムがよく合いますよね」 「……ああ」 「昨日作ったベリージャムがあるんですよー」 棚を開けて、ジャムの瓶を取り出した。 果実を砂糖と煮詰めた自家製ジャム。メレディスの朝食には欠かせないものだった。友人にも好評で、ベリー系以外にも、りんご、オレンジなどでも作っている。 「……よく、作るのか?」 「はい。お菓子作りが趣味なんです」 ここまで、メレディスは笑顔を崩さなかった。 ミキはずっと眉を寄せた険しい表情で、悪く言えばしかめっ面だ。見ようによっては、睨まれていると思うネコの方が多数だろう。 それでも不快な印象を抱かないのには、やはり、このひとは優しくていいひとだという先入観があるからだ。 今もこうして、メレディスの申し出を受け入れて、お茶に付き合ってくれている。だから、このひとはいいひとだと。 そう、メレディスは、一言で言えば楽観的なのだ。 基本的に、全ての事柄をプラスに考える。 だから、ひとに悪印象を抱くことはほとんどないし、誰に対しても親しみを持って接する。優しさには優しさが返ってくるのだと信じている。 自分が笑顔でいれば、周りも笑顔になる。 笑っていれば楽しいし、悲しい気持ちはやってこない。 メレディスは、そう『信じて』いるのだ。 「お口に合いますか?」 その問いに、ミキは確かな頷きで返した。 表情がほんの少しだけ緩んだのを、メレディスはしっかりと見ていた。 そして、また微笑む。 自分が笑っていれば、このひとも、きっといつかは笑ってくれると。 「それはよかったです。たっぷりつけちゃってくださいね」 言って、何もつけないままのスコーンを一口頬張る。 スコーンそのものは簡素な作りで、何も混ぜ込まれていないプレーンの生地だ。味はかすかに甘いくらいで、ほとんど生地の味だったが、物足りなさは感じなかった。このままでも十分美味しいと言える、優しく素朴な味だった。 「とっても美味しいです。手作りですね?」 「……ああ」 やや不揃いな形は、手作りならではと言える。 メレディスが普段作るのは、ケーキやタルトがほとんどで、たまにクッキーを焼くこともあるが、スコーンやマフィンなどのシンプルな焼き菓子は、あまり作ることがなかった。 今度作ってみようかな、と考えながら、向かいに座るミキの顔を見た。 目が合うと、僅かに目を見開いて、それから気まずそうに逸らされたが、メレディスは変わらずに微笑んでいた。 それから一時間。 花屋の昼休憩の時間が終わる頃まで、お茶を飲みながらのんびり過ごした。 会話はほとんどなく、また途切れ途切れだったが、メレディスは穏やかな笑みを絶やさなかった。 ミキは、短く相槌を打ったり頷いたりしながら、店内に置いてある花を見ていたり、メレディスが違う紅茶を淹れると、何やら考え込んでいる様子で味わっていた。口に合わなかったというわけではなさそうだったのだが。 「……そろそろ、失礼する」 「はい。お付き合い頂きありがとうございます」 ミキは、昼休憩が終わる時間を知っているのか、時計の針が13時を指す少し前に、そう言って立ち上がった。メレディスも見送るべく立ち上がる。 店の前まで出ると、ミキはメレディスの顔をちらと見て、軽く会釈した。 「いつでも来てくださいね。待ってます」 それに笑顔を返す。 メレディスの言葉をどう受け取ったのか、ミキは、僅かに俯いた。それから、「……ああ」と低い声で頷いた。 「あ、言い忘れたことが」 踵を返そうとしたミキを引き止めるように、メレディスの言葉。 ミキは無言でメレディスを見つめる。 一呼吸の後、 「たくさんの綺麗なお花たちをありがとうございました」 ぺこりと、礼儀正しく一礼した。 「いや」 ミキは首を振る。その挙動には、戸惑いの色が見られた。 「いつも楽しみに待ってたんですよ」 「……そうか」 「嬉しかったんです、ほんとうに」 メレディスの笑顔から逃げるようにミキは目を逸らす。目を細めて、顔を覆う外套をぐいと上に引っ張った。 「よかったら、これからも……わたしに花を贈ってくれませんか?」 その言葉に、ミキの動きが一瞬止まり、 「……いいのか?」 と、目線を下に移して言った。 「はい」 優しい声音で、確かに告げる。 「わたしの知らない花たちのこと、もっと教えてください」 「きっと、……俺のほうが知らない」 ミキは目を閉じ、首を横に振った。 メレディスは静かな声で言う。 「いいえ、あなたは知っています。大空と、荒野と、自然……わたしの知らない、外の世界を」 街には育たない花。 外でも珍しい花。 その花たちを取り巻く大自然と、外の世界。 ミキはそれを知っている。 薬屋なら、よく効く薬草を採取するために、頻繁ではないにしろ、外に出ることは多いはず。 その際、ネズミやオオカミと戦うこともあるだろう。 メレディスには全く縁のない世界。 そんな、自分に知らないことを知っているのだから、ミキはすごいと。 メレディスは、純粋にそう思っていた。 しかしミキは、 「空は……ここにある」 言うと、上を指差した。 太陽の光降り注ぐ表通り。 それは今ここに居る二人にも平等に降り注ぎ、天を見上げたミキは、眩しそうに顔をしかめた。 「……そうですね」 メレディスも空を見上げ、そしてほんの少しだけ、悲しそうに笑った。 その表情の変化は微々たるもので、彼女に近しい者でないと気付きそうにないものだったが、 「大丈夫、か?」 ミキが、メレディスを見つめた。 その言葉に、 「……?」 いつもの笑顔に戻ったメレディスが、首を傾げる。「わたしが、どうかしましたか?」と、明るい声で言う。 彼女は、無意識のうちに、気持ちに蓋をしていた。 何でもないと。悲しくない、だから笑える。 心の中で何度も言った。 「……いや」 ここでミキが何を思ったのか、メレディスには分からなかった。 一つだけ分かったのは、自分を心配してくれたということ。 それを嬉しくも、申し訳ないとも思いつつも、何も言葉にすることができなかった。 「じゃ……」 「はい、また」 今度こそ踵を返し、ミキは歩き去っていった。 メレディスは、小さく手を振りながら、その姿が見えなくなるまでそうしていた。 見えなくなると、静かに手を下ろし、小さく溜息をついた。 そして、休憩中の看板を、店の中へと戻すべく、よしっと一人頷いた。 今日は、花の贈り主さんと会うことができました。 ミキさんは無口で、いつも難しい顔をしていますが、優しくて、いいひとでした。 花が好きで、お菓子が好きで。 アルヤたちに聞いた通り――わたしの、思っていた通りのひとでした。 仲良くしてくれるでしょうか。これからも、姿を見せてくれるでしょうか。 信じなければ何も始まりません。 だから、わたしは信じます。 いつか、笑顔を見せてくれることを。 でも、本当は不安でした。 だって、ミキさんがなぜわたしに花を贈り続けてくれていたのか、分からなかったからです。 それから。 ……みーちゃんじゃ、なかったから。 ミキさんは花が好きで、だから、花が好きそうな『花屋』に、花を贈ったんだって。 今は、そう思っておくことにします。 他に理由があるのなら、いずれ聞けたらいいなと思います。 わたしはこれからも、ミキさんが止めない限り、花を待ち続けます。 みーちゃんじゃなかったけど、ミキさんのくれる花たちは、みーちゃんみたいに、わたしに元気をくれるから。 そうだ。 今度は、わたしの作ったケーキをご馳走しましょう。 どのくらいの甘さが好きなのか分からないから、少しクリームを控えめにして。それとも、フルーツをたくさん載せたタルトにしましょうか。 次にお会いできるときは……たくさんお話がしたいです。 ミキさんのことが、もっと知りたい。 袋に書いてあった薬屋――『ルクリス』のことも……。 せっかく知り合えたのですから、仲良くなりたいと思うのは当たり前のことですよね? わたしの、新しいお友達。 これから、よろしくお願いしますね。ミキさん。 |
||
 |
 |
 Back
Back