 |
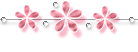 |
 |
|
―――――― ミキは夢を見ていた。 その夢で彼は小さなちいさな子供で、彼より少し年上の少女と向かい合って座っていた。 「ねぇ、やくそくしよ」 ミキは言う。少女は首を傾げて彼を見つめた。 「やくそくげんまん。かなしいかおはダメなの、わらっていて。そしたらかなしいのなくなっちゃうんだよ」 涙に濡れた少女の頬を撫でて、ニッコリとミキは笑ってみせる。 「みぃもがんばるから、がんばって。あのね、わらってね、わらってて。すきなの、わらってるとこ」 撫でられておっかなびっくりの少女。でも、少し嬉しそうに「うん」と頷いて、ミキは手をぱちんと叩き「よかった!」と笑う。 「今はたくさんないても、おわりはニコニコしなきゃダメだよ。かなしいのがふえちゃうから」 「……うん、なかない」 「みぃもね、かなしいのから、まもったげるから」 彼はふにゃりと笑って、自分より少し背の高い少女に抱きつく。髪からあまいあまい花の香りがして、ミキは嬉しくなった。 「だいすきだよ」 少女の名前を呼んで、何故だか再び泣き出してしまった少女の背を優しく撫でる。 「みぃ、ずっといっしょだからね」 夕日に染まったその場所で二人小指を結んだ。 ――――――― 昨日も夜半過ぎまで薬学書を読んでいた。いつもの事とはいえ連日はさすがに辛くなってきたのか、最近はよく居眠りをしてしまう。居眠りをしていても店を訪れるのは近所のネコばかりで、自分を優しく起こしてくれる為、問題はない。が、店番としては全く宜しくない。 「今日はちゃんと寝よう」 決意も新たにあくびをしながら背を伸ばすと ばきり 椅子が悲鳴をあげた。慌てて元の体勢に戻って深呼吸。振り向いて問題がない事を確認し、ほっと息をついた。 17歳になったミキの背はもうすぐ2メートルを越す域に達していた。4年前までは何も問題はなかったのだが、ここ最近また背が伸び、更に体格がしっかり――ゲリー曰くどっしり――としてきて、今まで使ってきた椅子は老朽化もあってそろそろ限界らしい。 ミキはそろりそろりと立ち上がり、椅子を奥の方へ引っ込めた。何事も壊れる運命にあるとはいえ、みすみす壊してしまうのは可哀想に思えたのだ。明日辺りに早々と買い換えて、長らく使ってきた椅子は感謝を込めてインテリアにして静かに過ごさせてやりたい。 「ミキくん!」 店の入口から声が聞こえ、そちらに視線を向ける。開いた扉から差し込む朝日が目に入ってきて誰かは視認出来ない。 「……だれ?」 「さて、誰でしょう?」 悪戯気な問いにミキは苦笑する。そして少し慣れた目が微かに上がった口角を見る。 「あ」 声が漏れた。 最近よく見るようになった夢が重なったのだ。 光の中で浮かび上がる小さな影。浮かんだ微かな笑み。風に揺れる髪。 「……どったの?」 「フリーダ?」 目が慣れると、そこに立っているのが幼馴染の少女である事が分かった。「大丈夫かい?」不安気に眉尻を下げ 、ミキをじっと見ていた。大丈夫だと笑うと不安そうにしながらミキに近付いてくる。だが「あ、わかった」ふいに笑うと、ミキの頬を突っついた。 「まァた寝不足だろー?勉強は程々にしろって言ったじゃないか」 「でも」 「でもじゃないよ。体調が万全じゃないのに門の外に行ったりしないかフリーダちゃんは不安ですよ」 「んー、大丈夫だよ」 「そこで行かないって言わないのがミキくんらしいよね。……って、この馬鹿者!」 ぺちんと緩く腕をはたかれる。痛みはないが、フリーダの鋭い視線にミキはタタラを踏んだ。 「最近オオカミが近くで出たって知ってるよね?今は絶対に駄目だぞ、そんな状態で外に行っちゃ絶対に駄目、許さないんだから」 口を真一文字に結び、ミキをじろりと睨む。慌てて謝ると「謝って欲しいんじゃない」と唇を尖らせた。どうしたらいいのかと考えあぐねているとフリーダは小指をミキに突きつけてくる。 「約束して、無理しないって」 やくそくだからね。 幼い少女の声が重なって―― 「もう!ほら、こうするんだぞ」 ぐいと手を引かれ二人の小指は絡められる。フリーダの細い指とミキの太い指だとどうもちぐはぐで結びにくかったが、なんとか繋いで口早にゆびきりの童謡を歌う。指を離すと同時にフリーダは「嘘付いたらやだよ」背伸びをしてミキの服の襟首を掴むと顔を寄せた。 「いい?またあの時みたいに死にそうになったら、今度こそ絶交だからね!」 「あの時って」 「あああっ!!みーくんとふーちゃんがエロいこギャン!!」 突如現れたのはミキとフリーダと幼馴染であるゲリー。迅速に動いたフリーダが妙な事を言い切る前にその尻を蹴り飛ばした。ゲリーは尻を押さえながら 、地面に這いつくばってしくしくと声をあげて泣き出した。 「妙な事言うなよ、ゲリーくん!きみがそうやって変な話ばかりするから、ぼくの親父が……っ、もういい!きみなんか尻に穴をあけて苦しめ!」 そう叫ぶや否やフリーダは出て行こうとするが、床に転がったままのゲリーを見つけると、再度尻を蹴り上げた。ゲリーは「尻が二つに裂けた」などと言いながらゴロゴロと部屋の端っこへ転がっていった。少し嬉しそうに見えたのは気のせいだといい。 「あ、フリーダ」 「なっ、なに?」 「何か用があったんじゃないの?」 問うとフリーダは視線を泳がせ「遊びに来ただけだよ」と低く言う。 「だったら上がっていって。ゲリーもいるし、みんなでお茶飲もうよ」 確か新しくブレンドした茶葉が残っていたはずだ。あれはなかなか良い出来だったし、気に入ってもらえるに違いない。ミキがそう言うとフリーダは微笑を浮かべたが「今度にするよ」首を横に振った。 「具合が悪いの?薬要る?」 「ん、大丈夫だって。ちょっと用事思い出したからさ、また今度淹れてよ」 「うん、よろこんで」 じゃあ、とフリーダが扉を開ける背を見ながら、ふいにミキは思い出す。 「フリーダ」 ミキの手には薄紅色の花が1束。「よかったら持っていって」薬を包む紙を引き寄せ、それで花をぐるりと簡易に包装する。そうして差し出された花を暫し見つめ「ありがと」受けとったフリーダの笑みに、ミキは同じく笑みを浮かべた。 「外へ行った時に沢山咲いてたから少しだけ貰ってきたんだ」 「ミキくんはお花が好きだもんね。ミキくんのお花畑もそろそろ満開かい?」 「んー、もう少しかな」 「そっか、今年も楽しみにしてるよ」 言って、フリーダは背を向け手を振りながら帰っていく。その背が少し小さく見えた気がして、ミキは首を傾げ 「みーくん!!」 その首にゲリーの腕が巻きついた。 「みーくんは鈍感ですね、まったく」 すぐに解放されたものの、ゲリーは眉間に皺を寄せて憮然とした面持ちでそう言う。だが、すぐに「ま、いいです」笑顔に戻った。 「で?花守魔王は今日もお花を配ってるんですね」 「みんなに外の世界を教えるのにはこれが一番いいかなと思って。ゲリーにもあげる」 手早く包んだ花を渡すとゲリーはくすくす笑いながら、それを受け取った。 花守魔王。それがミキの二つ名だ。畑の一部に作られたミキの花畑は近所では少し有名で道端に咲く花もあれば、ミキすらも名を知らぬ花、赤い花、青い花、黄色い花、大きな花、小さな花、なんでも揃っている。理路整然としたものではなく自然に溶け込むような形で作られたそこで彼はよく本を読んで過ごしていた。そうやって出来た二つ名は花守魔王。絵本に出てくる魔王と似た姿のミキ、けれど魔王とは程遠い穏やかな性格の彼が花畑の平和を守っていると近所のネコ達が冗談混じりで言ったのが始まり。 他にも採取の時に咲いている花を摘んできては仲の良い客や近所のネコ達に配りもする。誰かに外の世界を見せたいミキの精一杯の行動がそれで、概ね評判もいいので4年前から続けている。 だが 「余るかも」 「余りますねー」 今日は客入りが少なく、もうすぐ昼だというのに花がだいぶ残っている。大きな花瓶に3つ分。このまま明日の分として置いていてもよいのだが、花の寿命を考えれば今日中に誰かに渡したい。ミキがそう独りごちると隣でお茶を飲んでいたゲリーが「じゃあ」立ち上がり 「みんなに配りに行きましょうよ。ついでにパトロールに付き合ってください」 「えっと、もしかして今までサボってた?」 「その通り!……って、みーくんってば溜息吐かないで!」 とりあえずゲリーを叱ってから、ちょうど帰ってきていた兄に店番を頼み二人は外へ出た。 最初に店周りのネコ達に配った。皆それぞれ嬉しそうに受け取り口々に「さすが花守魔王さん」とミキに言う。褒められているのか、貶されているのか分からないが、とりあえず「ありがとう」と笑っておいた。 一時間程かけて花瓶二つ分を配り終えたが、残りの一束に困った。近所のネコ全員に配ってしまって他をあたるしかないのだが、生憎ミキは人見知りであるから近所以外の付き合いが殆どない。 「ハンナにあげたらどうでしょう?」 頭を悩ませていたミキにゲリーはそう提案する。 「あ、そっか、ハンナちゃんか」 ハンナ・ヘドリックは、肩ほどまで伸ばした茶髪をリボンで二つに結んだ可愛らしい少女である。そしてミキの小さな友人だ。少女は表通りの教会で牧師とその妻と共に住んでいる。だが、教会を司る牧師の子ではなく、元々はノラネコだったという。親と共に旅をしていたらしいが、荒野でオオカミに襲われハンナのみが命からがら街へ逃げ延びた。それを救ったのが牧師で、以来ハンナは教会の子として過ごしている。 教会の子とて、元はノラネコだったせいか血気盛んで、孤児ということからイジメを受けるも彼女は小さな体で全員を殴り飛ばしたらしい。それから彼女はガキ大将として街を駈け回っては友人という名の舎弟の世話を焼いている。つまるところ 「今日は何処にいるんだろう」 居場所が特定出来ないという問題があった。しかも彼女は極度の方向音痴の為、迷子としてギルドの世話になる事が多く、その居場所は更に判りづらい。 今日もギルドの本部で遊びまわっているかもしれないと二人は苦笑しながら表通りへ向かって歩き出したのだが「あ、噂をすれば影ですよ」二人の前方から麦穂の色をした髪の小柄な少女と、件のハンナが何やら楽しげに話しながら歩いて来ていた。ハンナはすぐに二人に気付き小さな手足を精一杯振って走ってくる。ミキが迎えるべくしゃがむと、ハンナはそこへ飛び込んだ。 「はなもりまおーっ!」 「こんにちは、ハンナ」 「えへへ、こんにちは、まおー!」 「今日も元気だね」 「うん、元気!」 まおーと呼ばれたミキは体を離したハンナの頭を撫でて持っていた花を紙に包んで差し出す。しばらく不思議そうに目を瞬いていたが、すぐに「ありがとー」それを受け取って満面の笑みで礼を言った。 「ハンナ」 上から少女の名を呼ぶ声がして、ミキとハンナは同時に顔をあげた。そこにいるのは麦穂色の髪をした少女。その頭上にはギルド員の証明たる灰色の帽子が見えた。どうやら今日もハンナは迷子になってギルドにお世話になっていたらしい。 「ねえ、それ、大丈夫なのかしら?」 「きれーなお花だよ!」 ギルドの少女は花の匂いを楽しむハンナに目をやって、それからミキへと視線を向ける。その視線には警戒の色が強く見えた。 「……」 どうしたのだろうかとミキが少女を見つめると少女の顔が一気に強張り、手が後ろのムチに伸びた。これにはミキも瞠目して身構えた。 「あるるん、みーくんは悪いネコじゃないですよ」 「あ、あぁ、あんた、ゲリー……?」 緊張した二人の間にゲリーが割り込む。 「その手にある物は必要ありません。顔は怖いですが中身は子供好きの優しい子ですよ。ね、ハンナ」 「そーだよ、まおーはいいネコ!顔は怖いけど」 「そう、なの?それは悪かったのだわ。でもこんなに悪役じみた顔なんてそうそう無いから……」 「えっと、そんなに怖い?」 強面薬屋の問に3人が揃って頷く。ミキは苦笑し、それから肩を落とした。 それからゲリーと少女は何事かを話し出した。聞いてもちっとも話が分からないので、おそらくギルドの仕事についてなのだろう。 ハンナが項垂れたままのミキに「まおーはよいこですよー」と慰めの言葉をかけ、そっと頭を撫でた。気恥ずかしくも嬉しくて、ミキはハンナを抱き上げる。ミキの小さな友人はキャアキャアと嬉しげに声をあげた。 「……どう見ても誘拐犯と子供なのだわ」 「見た目なんて所詮見た目でしかないんですよ」 声を潜めているつもりらしいが、よく聞こえている。ミキが苦笑いでギルドネコ二人に目をやると慌てた様子で首を振った。 「それで、あるるんは」 「その呼び方止めて頂戴。アルトマイヤー・リヴィエール。それがあたしの名前なのだわ」 「じゃあ、アルトマイヤー・リヴィエールは」 「融通の効かないネコね!アルヤでいいのだわ!」 「じゃ、そのアルヤはハンナと何してたの?ナンパ?」 何処か勝ち誇ったかのようなゲリーの足をアルトマイヤー・リヴィエールことアルヤは思いっきり踏んづけた。ゲリーが悲鳴をあげてミキの後ろに隠れると「暴力反対。っていうか、おれの周りの女の子ってみんなこんなのばっかだ」そんな事を涙声で。ゲリーにも問題があるんだよと言いたかったが、どうせいつもの通り「海原を泳ぐ魚なんです」という不可解な言葉で笑い飛ばされるのでやめておく。 「どういう思考でそうなるのかしら!あぁ言わなくていいわ、馬鹿が移りそうだもの!」 すっぱりと切り捨て、アルヤは息を吐く。 「あたしはハンナを教会に送ってあげていたのだわ」 「え、でも教会は反対」 「へっ?」 「表通り」 あまり知らぬ相手と面と向かって話すのはどうにも苦手で、ミキはアルヤから目を逸らし、声を低く、言葉少なに言う。 「で、でもハンナはこっちだって……」 目を瞬き、アルヤが言葉を濁した。ちらりとミキの肩に乗ったハンナを見て、口を開きかけ 「迷子に道案内させてるんですか、あるるん」 アルヤが何かを言う前に言葉の端々に嘲笑を含ませゲリーが言う。アルヤが睨むもゲリーは気にせず意地の悪い笑みを浮かべている。もちろんミキの後ろで。 「俺達が連れていく」 今にも腰に備えた鞭を振るいそうなアルヤにミキはハッキリした声音で言う。アルヤの眉がぴくりと跳ねた。 「あんたが?」 「今から表通りに行く。俺達と一緒なら人波に浚われることもない」 「それはそうだわ。でもあたしはあんたを信用していないのだわ」 ふん、と鼻息荒くアルヤ。ミキに肩車をされたハンナが「まおーはハンナのおともだちですよー」とワタワタと手足を揺り動かして抗議しているが、アルヤは「だーめ」口にひとさし指を当て静かにするように伝える。ぷぅ、とハンナが息を吐いた。ミキからはハンナの顔は見えないがきっと頬を膨らませ拗ねているのだろう。 「じゃあゲリーは?同じギルド員なら問題無いと思う」 ミキが問うとアルヤは眉間に皺を寄せた。 「あいつとは顔見知り程度。あんなヘラヘラした同僚を信用出来ないのだわ」 「あ、ひどいひどい、あるるん、ひどい!」 ミキの後ろから出てきたゲリーは憮然とした表情で抗議の声をあげる。「ま、いいですよ」 「信じてって言っても通じないなら」 背を伸ばし、にやけていた笑顔を引き締め、ゲリーが言う。 「ここは任せて巡回に戻りなさい、アルトマイヤー・リヴィエール」 よく響く声で。 「ふん、何様のつも……ハァっ!?」 「ほらほらぁ、あるるん、上司命令ですよぉ」 胸元から取り出した中尉の証たる手帳を見せつけながら、代々ギルドに従事するグレン家跡継ぎジェラルド・グレンはにんまりと笑ってみせた。 あれからアルヤは始終渋い顔で「はい」だの「ああ」だの身の入らない声で答え、早々と立ち去っていった。ミキがその背を追いかけ、持っていた花を渡すと少し驚きはしていたが素直に受け取り「ありがとう、綺麗なのだわ」穏やかな笑みで礼を言ってくれた。 「悪い人ではないんだね」 「そりゃそうですよ。ギルドなんて下手すれば命懸け!そんな所に悪い奴が入り込んでるなんて事ぁ無いです、ないない」 大通りに向かう道、隣を歩くゲリーがけたけたと笑った。 4年前まで彼は怠け癖のあるギルドネコだった筈だというのに、齢22にして中尉。アルヤが去った後に何があったのかをゲリーに聞いてみたが「えーっとね、うん、ひーみーつっ」だそうだ。代々ギルドに身を置いている家柄だけあって、そういった才能があったのかもしれない。ミキは純粋な尊敬の念で賞賛を口にしたがゲリーは聞き流すかのようにアクビをしていた。 「別に偉くなんかないです。おれは何も変わりませんよ、みーくんの親友、それだけでいいじゃないですか」 曰く、特別扱いは嫌い、そういう目で見られるのが気に食わない。自分は変わらず自分なのだから普通に接して欲しい。――だそうだ。 「さっきのはみーくんが疑われてるのに腹がたったんです」 だから権力を行使したのだと少し気まずそうにゲリーは言う。 「でもでもでもー!すっごくかっこよかったですよ、げぼくにぃ!」 ミキに肩車されたままのハンナが嬉しそうに言う。ゲリーは眉間に皺を寄せ顔を歪めた。 「だーかーらー下僕ってなんですか、下僕って」 「いちばんたよれるネコのこと!ししょーが言ってたです!」 「えー、またあの人ですかー……」 はぁと溜息を吐いて「ハンナに要らない事ばっか教えるよなぁ」と肩を落とした。 「いらないことじゃないよ、ししょーはすっごいんだから!たたかいかたおしえてもらったの!今日だってね、そのおかげなの!」 「でもね、ハンナ。あまり無理しちゃ駄目だよ。怖いと思ったら逃げなきゃ」 「でも、あのおねーさん、ええと、きんいろおねぇが来てくれたから!」 きんいろおねぇはおそらくアルヤの事だろう。まおーといい、げぼくといい、ハンナには独特のセンスがあるようだ。 道すがら肩車に気を良くしている彼女の話を聞けば、数人の少年にいじめられていた小柄な少年をハンナが助けたらしい。ハンナはまず少年を逃し、いじめていた少年達と相対峙した。数は4人で全員がハンナより年上、体も大きい。まともにやって勝てる相手ではないと分かっていたが、勝率など彼女の考えの中にはなかった。敵対している者には牙を剥け。それがノラネコの生き様だと親に教えられた。そう、ハンナは寂しげに言う。 「そこにね!きんいろおねぇがやってきてね、みんなやっつけたの!」 強かった、格好良かった、大人になったらああなりたいとハンナはそれは嬉しそうに言い、ミキも微笑みながら同意する。人々の平和を守るギルドネコは幼いながらに誰かを守ろうとするハンナにぴったりの職だろう。 「ゲリーもそう思うよね?って……ゲリー?あれ?」 同意を求めた親友の姿が隣にない。後ろに目をやるとゲリーが数歩前で立ち止まり、じっと何かを見つめていた。 表情は希薄、表情がくるくると回る彼が見せた初めての事にミキは声を掛けることを躊躇った。そしてゲリーは何事かを呟く。その声はミキの耳まで届かない。だが、ふいに 「あ、ええっと!ベアト様!ベアトリス様!」 いつもの笑顔に戻りゲリーは声を上げて、誰かの名を呼び手を振る。目線の先――糸目なので何処を見ているかイマイチ分からないが――を追えば、長く真っ直ぐな銀髪を一つにまとめた見目麗しい女性が手を小さく振り替えしていた。その頭上にはゲリー、アルヤと同じくギルドの帽子。 「ねえ、ゲリー」 「あ、みーくん?ごめん、ちょっと先輩見つけたから挨拶しよーと思いまして。ちょっと待ってて」 にっこりと笑うグレンの様子はいつもと変わらない。先ほど見た姿は夢や幻だったのではないかと思える程、その雰囲気ががらりと違う。 「ゲリー、さっき……」 「ごきげんよう」 ミキが問おうとした時、すぐ近くで女性の声がした。はっとそちらに目をやれば先程見た銀髪のギルドネコの姿。 「グレン中尉、巡回ご苦労様」 銀色のギルドネコ――ゲリーが呼んだ名前の通りだとすればベアトリス――はミキの存在に気付くと、長いまつげを伏せ静かに会釈をする。慌ててミキも頭を下げた。肩に乗っていたハンナがニャアと悲鳴をあげる。 「貴方とははじめまして、ね。中尉のお友達かしら。私はベアトリス・ボールドウィン、皆からはトリスと呼ばれています。グレンは違うけれどね。彼とは違う管轄だけれど、大尉として彼とは仲良くさせてもらっているわ。以後良ければお見知りおきを」 長いスカートの裾を指でつまみ、軽く膝を曲げ優雅に一礼。その礼は本などでよく見る貴族の礼で、ギルドに従事する者がそういった事をするとは思っておらず、ミキは躊躇い、何を言えば良いか分からず、結局唸り声を少し上げた程度だった。頭上のハンナは「おぼえた!んっと、べあさま!ハンナです、よろしくおねがいします」既に彼女は持ち前のセンスで呼び名を決定している。伸ばされたハンナの小さな手をトリスは取り「よろしくお願いします、ハンナちゃん」微かに笑みを浮かべた。 「ベアト様」 ハンナが満足気に手を退いた時、ゲリーが弾んだ声でトリスに声をかける。 「今日はお一人なんですね。さっきリヴィエールと裏道で会いましたよ。いつも二人でいらっしゃるから珍しいなと思いました」 「えぇ、今日は会議があったから巡回をアルヤ一人でお願いしたの」 「あ、会議ですか」 連絡来てなかったけど、とゲリーが首を傾げる。 「会議というより大尉以上の官職に同意を求めていた、というところかしら。あなたの同期、クライヴェルグ・エイジェルステットを少佐に引き上げるべきかという話ね」 「あ、くぅくんですね。早いですね、もう少佐ですか」 「ええ、早すぎるわね。貴方ですら中尉だというのに明らかに時期尚早よ。過大評価もいいところだわ」 ふ、とトリスは息を吐く。ゲリーは少し考えたように目線を落とし、それから首を振った。 「誰が見ても彼の能力はずば抜けて高くて、まあ、稀代の天才って呼ばれるだけのネコですし、妥当な評価だとおれは思います」 「そうね、能力的にいえば同期の誰にも追随を許さないかもしれないわ」 小さく頷き、トリスは言う。 「でも彼の内面は未熟よ。普段は冷静だけれど、時に我を忘れて飛び込んでいってしまう。それを切り抜けてきた事はさすがという所だけれど、彼が敵わない相手もゴマンと存在しているの。少佐となれば多くの部下を従え、指示しなければならないのだから、絶対に激情に流されてはならない。――私は彼を認める事は出来ないわね、上に立つ者としては相応しくないわ。だから反対しておいたけれど、明日になれば正式にクライヴェルグ少佐になっているはずだわ」 流れる言葉にゲリーは一瞬視線を逸らし、だがすぐにトリスに視線を合わせると 「随分と辛辣ですね」 ほんの少しだけ暗い声をしていた。 「あら、そう聞こえた?同僚としての率直な意見よ?」 「――――そうですか」 穏やかに微笑むトリスを見ているゲリーの笑みに陰りが見えた気がしたのは杞憂だろうか。どうもトリスと話しだしてから様子がおかしいのだが、ミキにはどうすればいいのか分からず、ただ会話をどうにか理解しようと耳を澄ます事しか出来ない。 「逆にグレイ中尉は過小評価されていると私は思うわ。あなたの隊の統率は素晴らしいものだし、士気も高い。貴方がもう少し真面目に事務に精を出してくれたらいいのだけれど」 「あー……、それって叱られてますか?」 「ええ、そうよ。ちゃんと仕事なさい、中尉。事務のネコから貴方について愚痴を聞くのは飽きてきたわ」 「え、あ、その、す、すいません……」 その後、あれこれとトリスからの注意を受けたゲリーは泣き出しそうな顔で俯いていた。トリスはそれに気付く事がないまま続け、ハンナがゲリーをあまりいじめるなと言うまで説教は続いた。 「くぅくん、えーっと、クライヴェルグ・エイジェルステットってのはおれの同期で、さっきのベアトリスさんの幼馴染なんですよ。で、そのベアト様はくぅくんの事が好きみたいで、ベアト様の1ファンたるおれは何とも複雑な気分なのでした、まる」 トリスと別れた後、ミキが先程のことを尋ねる前にゲリーがそう教えてくれた。いまいち納得いかないが、彼がそう言うのだからこれ以上聞くわけにはいかない。からからと笑うゲリーの隣でミキは口をつぐんだ。 「げぼくにぃは片思いなの?」 「ははん、ただの1ファンに片思いもなにもありませんよーだ」 「むー、、つまんないのー……」 肩車されたままのハンナがじたばたと足を揺らした。ミキが慌ててハンナが落ちないように膝を掴まえる。 ミキの片手には花束がまだ少し残っている。トリスと別れた際にも渡したのであと少しというところだ。トリスは切れ長の目を細めて「あら、アドニスね」ミキの知らぬ花の名前を言いほんの少しの笑みで礼を告げた。その一挙手一投足もやはり凛としていて、他のギルド員とは違っている。ゲリーにそう言うと、彼女は貴族出身だと教えてくれた。今は社交界を離れギルドに籍をおいているがその意図は不明だという。 「権力を持っているから次は武力を手に入れたいんだ、とか言われてますが、彼女がそんな事の為にやってるとは思いませんけどね」 そういう噂はただの嫉妬でしょう。 つまらなさそうに言い、ゲリーは溜息を吐いた。 大通りに出ると目眩が起こりそうな程の人混みだった。通りに出る事を躊躇うも親友はミキの心情などお構いなしでどんどん進んでいく。頭上ではハンナがしきりに「しゅっぱつしんこー」とミキの頭をぽんぽんと叩いている。息を大きく吸い、ゲリーの後を追う。 「みーくん、顔怖い、いますごく怖い。なんていうかガリガリって食べられそう、頭から」 青ざめるゲリーと、眉間に目一杯の皺を寄せ、更に目を細めて、肩をいからせたミキ。ミキはいつも着込んでいるマントで口元を覆い、吸ったままだった息を思いついたように一気に吐いた。 「ひとが沢山いる。……怖い」 「たぶん周りのひとの方が怖がってるよ、みーくんの事」 そんな事を言われてもミキに為す術は無い。見知らぬネコが苦手なミキにとって常に人がごった返している大通りは実に恐ろしい場所なのだ。恐怖で身体中が緊張して、つい眉間に皺が寄ってしまう。それによって自分の顔が魔王と呼ばれるに相応しいものに変わっている事は知っているが、だからといって自分でどうにか出来るものではない。 「周りがみんな退いて歩きやすいから便利なんですけどね……」 苦笑しつつゲリーが南へと向かう。南門の近くにハンナが住む教会があるのだ。 歩き始めてから、周囲のネコがミキを避けていくため通常10分かかる所5分で教会へと辿り着き、庭の手入れをしていた牧師へハンナを預けた。牧師はハンナが語る武勇伝に苦笑いを漏らし、届けてくれた二人と、それから助けてくれたアルヤにと手作りのお菓子を何個もプレゼントしてくれた。子供向けの朗読会の際に配られるそれは大人達にも人気でミキも数回しか食べた事がない。 「ありがとうございます」 ミキがそこでようやっと笑みを浮かべると、牧師は先との雰囲気の違いに大層驚き、笑顔を見られた事を喜んでいた。いつも不機嫌そうだから嫌われているのかと思ったのだと彼は困ったように笑い、時間がある時に遊びに来て欲しいとミキの手を握り言ってくれた。 怖いと思っているこの場所には優しい人が沢山いるのだ。 ミキは嬉しくて、牧師の手を握り返し、もう一度笑ってみせた。 「コンペイトウですよ、ほらほら」 巡回に戻るべく大通りを歩いていると、ゲリーが牧師に貰った包みを開いていた。 「あとクッキーもありますね!うふふ、今日は厄日かと思いましたけど収穫は素晴らしいです!」 赤色のコンペイトウを口に入れたゲリーは満面の笑みでそう言う。 「このまま何事も無く寮に帰れたらいいな。あとくぅくんに会いませんように!あの子ってばいっつもおれに注意という名のいじめをしてく……はい、厄日!今日厄日!!!ちくしょう!!」 「何をしている、ジェラルド」 「巡回ですよ、くぅくん」 二人の前に現れたのは濃い紫の髪に赤眼を持つ眉目秀麗の青年だった。その頭上を飾るのはやはりギルドたる証。 青年はゲリーを睨みつけると「その妙な名で呼ぶなと言っただろう」端正な顔を不機嫌気に歪めた。 「はいはい、じゃあエイジェルステット大尉サマでいいですか」 なげやりにゲリーが言えば 「気味が悪い」 更に眉間に皺を寄せてしまう。 おそらく彼が件のクライヴェルグ・エイジェルステット、若いながらもその才気から大尉から少佐へと引き上げられる稀代の天才。そしてこの見目だというのだから天は彼を溺愛しているに違いない。ミキの周りにはそういったタイプの男性はいない為、思わずじっと見つめてしまっているのだが、当人はミキの存在に気付いておらず、ゲリーと話をしている。 「言わせておいてそれですか?じゃあ、くぅくんでいいでしょ」 「何故そうなる。よくないに決まっているだろう」 「うっさい、くぅくんの方が可愛いんです」 「男が可愛いくてどうする。……おい、聞け」 耳を塞いで、ミキの後ろへと逃げ込んだゲリーに青年が言う。 青年がゲリーに手を伸ばし 「……」 だが、刹那、飛び退いた。 「…………おまえ、……」 「え?」 青年がじっとミキを見つめる。その表情は険しくミキは先ほど解れた緊張を再度感じた。眉間に皺を寄せ青年を見つめ返す。 「っ」 青年の細い肩が跳ねた気がした。 「くぅくんも、うちのみーくんを敵視ですか?やめてくださいよ、見た目で判断とか」 「……おまえの知り合いか?」 「幼馴染で親友ですよ。さっさとその剣収めて下さい、物騒な」 いつの間にかミキの前に立つ親友と、いつの間にか細身の剣を抜いていた青年。展開についていけず、ミキがゲリーの肩を叩くと「すいませんね、うちのボス、ちょっとボケてるんです」くつくつと笑う。 「誰がボケているというんだ。おまえだろう、ボケている馬鹿は」 「ボケで馬鹿って、他人を二重否定って!!」 「事実だ、サボり魔」 「サボってないです、ちょっとしたリラックスタイムなんですぅ!」 「それが問題だと言っているんだ、理解しろ」 「この糞真面目!そんなだから友達いないんですよ!」 「い、今その話はしていないだろうが」 一瞬見せたたじろぎを見つけてゲリーがほくそ笑む。青年はぎりりと歯を食いしばったが無視をする事にしたらしく、ミキへと歩み寄り「先程は無礼を働いた。すまないな」手を伸ばしてくる。 「……いや、仕方ない」 その手を取りながら強面薬屋は首を振る。 「クライヴェルグ・エイジェルステット、それがオレの名だ。クライヴとでも呼んでくれ。ジェラルドとは同期で、色々と世話になっ――世話をしている」 「ああ、それは申し訳無い……」 ゲリーがひたすら青年――クライヴに迷惑をかけている姿が目に浮かんで、ミキは深々と頭を下げた。ミキの後ろから出てきた件の迷惑なネコが「なんで謝るんですか!ていうかくぅくん事実と異なる事を言わないの!」ぶぅぶぅと文句を言ってきたが、二人は気にしない事にしておいた。少し悪い気もしたが、ゲリーも心得たらしくすごすごとミキの後ろへ戻っていったので問題は無いだろう。何故後ろに行くのか不思議だったのだが、どうやら目の前にいる上司たるギルド員が苦手らしい。時折視線を寄越すものの表情は暗いままだ。何か後ろめたい事でもしたのかもしれない。 「人の動きが妙だったから見に来たんだが、そうか、きみがいたせいだな」 「あ、それは……」 「ああ、きみは悪くはない、気にしなくていい。気になって見に来ただけなんだ」 「……お仕事おつかれさまです」 「きみも奴の巡回に付き合わされて疲れているだろう。――ジェラルド」 「はー?」 「オレと来い、寮に戻「やだへんたい何かされちゃうみーくん助け「死ぬか?」さーせん、大尉!!」 幼い頃から見てきているがやはり身の切り替わりの早いネコだなと、、目の前で交わされる言葉の応酬を見ながら思う。無言で睨みつけるクライヴとニヤニヤと笑うゲリー。仲が善いのか悪いのか分からないところだが、関係は良好かもしれない。 「なんでおれがくぅくんと一緒に帰らなきゃ駄目なんですか、きめぇです」 「ここから先の道はオレが見て問題が無い事を確認した。巡回はこれで終わり、おまえは今から寮に戻り書け」 「ポエムですか」 「書きたければ書け。だが今からおまえがギルド員として書くのは前日の強盗事件の始末書だ」 「よぅし、逃げま――って、みーくんどいて!そいつから逃げれない!」 おそらくこの場合はこうすべきだろう。踵を返すゲリーの襟首を掴み、そのままクライヴへと引き渡す。クライブは鼻でそれを笑い、がっちりとゲリーの襟首を掴む。 「ありがとう、世話をかけた。……帰るぞ、ジェラルド」 「アッー!」 きっとクライヴなら彼の怠け癖をなおしてくれる――といいな、とミキは離れていく二人を見ながら願うのだった。 クライヴとゲリーを送る際に持っていた花束を二束に分けて一束をクライヴに渡した。 助けて貰えると期待していたらしいゲリーの視線を感じながら包装したそれを渡すと、クライヴは「男から花をもらうとはな」少し困惑していたようだが「ありがとう、貰っておく」綺麗な笑みを浮かべ花束を受け取ってくれた。 「花か……――」 「……気に入らない、か?」 「いや、そうじゃない。オレの友人にも花が好きなネコがいるのでな」 じっと花束を見つめ何かを考えている様子のクライヴ。――そんな大きな隙を彼が見逃す筈がなかった。 「いえぁ!!!」 「っ!!!!待て、このサボり魔!!」 逃亡者ゲリー、ハンタークライヴ。 小さくなってゆく背をミキは小さく手を振って見送ったのが数分前。 大通りに嫌気がさしたミキは裏通りに戻っていた。曲がりくねった道と少し埃っぽい匂いが妙に落ち着く。ぶらりぶらりと見知らぬ道を歩く。 「あと一人分」 呟いて手に持った花束を掲げた。花びらの紫と傾きつつある太陽の赤が混ざる。 「誰か花の好きな人いたかな」 赤く染まった密集する家々の屋根を眺めながらぼんやり考える。近所以外の付き合いが殆ど無いミキ。思い浮かぶのは幼い頃から行きつけの喫茶店やケーキ屋といったところだが、今から行ったのでは着いた頃には閉まっているだろう。だとすれば、もうこの花は家に持って帰った方がよいのだろうか。 「……ん」 ふいに嗅ぎなれたパンの香りが鼻腔をくすぐった。 この独特の香ばしい香りはミキの家でよく買うパンの匂いだ。その店は薬屋から東にある。つまり 「まずい、ここ東の方だ」 足を止め、頭を掻く。やはり歩き慣れない道は来るものではなかった。この分では家に着くのは日が暮れきった頃になるだろう。 これ以上迷わないようにと嫌々ながら表通りへ出る道を耳を頼りに探す。存外簡単にその道へ出る事が出来たミキの目にそれが映った。 「…………」 手に持った花を見る。 「花が好きな人……」 ミキの視線の先には一見の花屋。 この道は頻繁という程ではないが通る事が多い道で、その花屋の事は開店時から知っていた。いつも穏やかな笑みを浮かべている女性がやっている可愛らしい外観の花屋だ。ミキ自身はその店に行った事はないが通りがかりにその女性の姿を見かけることが多い。いつも一生懸命に店を切り盛りしている姿は同じ店を営む者として好ましかった。 花の様子をこまめに見て、時に花に話しかけ、掃除も丹念にしている。誰かのために花を選ぶ姿は真剣で、けれど笑みは崩さない。 ミキの彼女に対するイメージは頑張り屋。毎日見ている訳ではないが、この花屋が閉まっている日をミキは見たことがなかった。 「……――」 もう一度手に持った花を見る。 「花屋さんなんだからお花好きだよね。きっと喜んでくれる、よね」 独りごちたミキはその花屋へと足を向けた。近付くにつれ、店主たる女性の姿が見えてくる。どうやら閉店の時間らしく外に出していた物を中へと運び入れている最中だった。毛先を巻いた青いセミロングの髪が動くたびに揺れている。 このまま声をかけて渡そうかと思ったが、ミキは顔を知っている程度だし彼女にからすれば全くの初対面だ。そもそも人見知りの激しいミキにそんな事出来るはずがなかった。 ミキは店主が中に入ったのを見計らい勝手口があるだろう裏へと回った。「よかった、あった」最後の花束を紙で包み「えっと」ケーキのラッピングを解いた時にポケットの中に詰め込んだままだったリボンで装飾をする。 「これで最後だし、それに……うん、まあいいや」 早くしなければ彼女に見つかってしまう。見つかってしまったらなんと言えばいいか見当もつかない。 ミキはそろそろと、けれど早足で店の勝手口まで歩き花束を置くと、近くの曲がり角で彼女がそれを見つけるのを待った。 不審がられてしまう可能性も高い。もし捨てられてしまうようだったら持って帰って大事にしてやろう。でも出来れば彼女に受け取ってほしいと思っている。――何故かはよくわからないが、なんとなく、そう思った。 やがて、足音が聞こえ彼女が現れる。息をひそめて、じっと見ていると彼女は一瞬驚いた様子だったが、花を手に取ると柔らかく笑んで 「ありがとうございます」 感謝を伝えた。 「っ!!」 慌てて体を引っ込める。 見つかったのだろうか、いいや、それはないはずだ。彼女の視線はこちらに一度も向いてこなかった。ならばどうして? もう一度見てみると、女性の姿は花束と共に消えている。がちゃりと金属音がして、鍵が閉められたのだと分かった。 「……喜んでくれた」 声に出すと、妙に嬉しくなる。 「ん」 嬉しいのに胸がキリキリと痛んだ。ちくちく、もやもや、きりきり、どきどき。 胸が苦しい。ここ最近無理をしていたせいで風邪を引いてしまったらしい。帰ったら薬を飲もうと一人頷きながら自宅である薬屋へと歩き出す。だが、ふいに立ち止まって振り返った。 「……また持ってきますね」 なぜだか彼女の笑顔がまた見たかった。 なんとか日が暮れきる前に辿りついた馴染みの裏通り。ミキがふぅと息を吐いたところで 「おっかえりー」 後ろからの声にミキは振り返り「ただいま、フリーダ」手を振る。今日は沢山のネコに会ったせいでフリーダの声や笑顔が懐かしく感じられた。 「花を配りに行ってたんだよ」 「うんうん、ゲリーから聞いたよ。全部渡せたみたいだね」 「みんな喜んでくれた」 フリーダが隣に並んで、二人は帰路への歩みを再開する。 「いろんな人に会ったよ、今日」 今日出会った人々の事を話すミキにフリーダはにこにこと相槌を打つ。しかし花屋の女性の事や変な気持ちだった事を話すと、フリーダは「それってさ」覇気の無い声でぽつりと言う。心配でフリーダの頭を撫でると困った顔でみ上げられた。 「ああ、ごめん、大丈夫だよ。ん、自分で気付けばいい事だから言わない。ぼく、関係無……くはないか、親友として」 「フリーダ?どうしたの?」 「あー、きみがあまりにも物事を知らなすぎる事に驚いているんだよ」 からかうようにフリーダは笑って、ミキの脇を小突いた。 「えっとね、先に言っておくけどさ、それ風邪じゃないからね」 「でももやもやする」 「大丈夫、みんな同じ事あるから。きみのしたいようにすれば治る、大丈夫だよ、ミキくん」 したいようにする。 何をしたいのかと考えてみて、それが花屋の彼女の笑顔を見たいという変わった欲求だった。そんな事で治るとはミキには思えず 「……よく分からないな」 首を振る。 「みんなもきっと分からない気持ちだからね、仕方ないよ」 フリーダはそう言って自身の胸元に手を置いて目を伏せた。気落ちした様子の彼女に何かを言うべきなのだろうが、よい言葉が見つからない。黙ってフリーダの頭を撫でるとくすくすと彼女は笑ってその手を握った。 「きみに心配されるようになっちゃったんだね、ぼくも。昔はぼくがいないと全然ダメな子だったのに」 「ずっと守ってくれてたから、今度は俺がフリーダを守るよ」 「あは、ありがと、嬉しいよ」 ほんのりと温かいフリーダの手がミキの手をぎゅっと掴む。 握った手を下ろし、子供の時のように手を繋ぎなおすと二人並んで歩く会話はそれから無かったが、それが不思議と心地良かった。 「また明日ね」 フリーダの店へと着いて、ミキは手を振る。フリーダも手を振り、店の奥へ入っていった。それを見届けて、ミキも薬屋へ急ぐ。今日は兄がいるから料理も豪勢に違いない。そういえばお腹が空いた―― 「ミキ!」 フリーダの声がして振り向けば、やはり彼女がそこにいて。 「あ、あのさ、今日もらった花の、その、花言葉」 「うん、知ってるの?」 「…………あ……いや、きみみたいな感じでさ!無邪気っていうんだ、清純無垢とか、きみみたいだよね!じゃなくて、いや、その、うん、気に入ったんだ。良かったらまた欲しいなって、それが言いたかったんだよ」 「うん、分かった。今度また取ってくる」 「……ん、ありがと。じゃ、また明日」 「ばいばい」 「ばいばい、またね」 太陽の姿はもう見えず、藍色の空には月が一人きり。だから沈んだ声をした親友の顔はよく見えなかった。 「あのね、ミキくん。あの花はね、期待、待望、はかない恋って言葉があるんだ。……期待してなかったんだけど、やっぱりちょっと寂しいかな。らしくないけど」 フリーダの小さな声は夜の闇が飲み込んでしまって、ミキへと届くことはなかった。  Back Back
|
||
 |
 |