 |
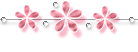 |
 |
|
―――――― 暗闇が何もかもを覆ってしまった。全てが壊されていく。消えてゆく。 「やだ」 身体中が冷えて奥歯が鳴り始める。指先は痺れてしまって痛くて仕方がない。 「……やだ」 だが逃げるわけにはいかないのだ。守らなくてはならない、この場所を。 「やくそくなんだから」 ミキは暗闇を睨み付けた。 ―――――― 「お、みーくんだ、おかえりなさい」 「ただいま、ゲリー」 ミキは5日ぶりに街に戻っていた。少し遠くへ採取に出たのはいいが、帰路へついた翌日嵐に巻き込まれ、3日で帰れるところ5日目の夕暮れにまで長引いてしまった。食料と水がやや心許なかったが途中で果樹を見つけたのが僥倖した。甘酸っぱい赤い果実を籠に詰めミキは飢えと乾きを凌ぎ、こうして余裕を持って帰還する事が出来たのだ。 「ほら、これ。美味しいよ」 籠に数個余っていた果実を門番をしていた幼馴染みに渡す。小腹が空いていたのだと彼は嬉々と受け取り早速かぶり付いた。 「あ、これ、ホント美味しいですね」 反応は至極上々。隣で物欲しげに見ていたもう一人の門番にも渡そうとすると、一瞬驚いて――おそらくミキの風貌に怯えて――目を丸くしていたが、ゲリーが「要らないなら貰います」と手を伸ばしたことで半ば反射的に果実を受け取った。「あの、あ、ありがとうゴザイマス」恐る恐る見上げられ、しどろもどろな返礼を貰い、ミキは会釈を返した。 「もう一つあるからゲリーにあげるね」 最後の一つを籠から取り出せば、それと一緒に薄紅色の花が飛び出した。それをゲリーが拾い、しげしげと見つめる。 「またお花を摘んできたんですね。……この量だと彼女の為ですか?」 花を籠に戻すゲリーに問われ、ミキは小さく頷く。幼馴染みはクスクスと笑い「じゃあ早く行かなきゃ駄目ですね」そう言って、二つ目の果実を受け取った。 門から街までは少し距離がある。二つの間には緑萌える草原があり、門から街に向かって行き交う者達の足が作り上げた自然の道が出来ていた。草原で帰り支度を始める露店を横目に、ミキは道を小走りに走る。 「近道しよっと」 呟いて道を逸れる。草原は完全に管理されたソレではなく、大人の膝丈以上に伸びた草も少なくない。だがミキの体格をもってすれば悪路に然程手間取ることもなかった。普通に道を歩いていては目的の場所へ着く頃には真っ暗になってしまう。それは出来るだけ避けたかった。 間に合うだろうかと空を見れば陽の姿はなんとか山際に隠れずにいる。なんとか日が暮れるまでには着くかもしれない。 早足の中、背負っていた籠を下ろし花を抜き出す。薄紅色の花びらを夕日の赤が照らし、まるで燃えているように見えた。見た事はあるが名前は知らない花。彼女はどうだろうか、知っているだろうか。それから 「喜んでくれるかな」 それは花屋の彼女に花を贈るようになって一月目の夕暮れのこと。 彼女の家に花を届け、家に辿り着いた時には空に煌々と月が輝いていた。別段寄り道をした訳ではないが、旅路の疲労から足取りは重く、結果いつもの倍の時間をかけて家に辿り着いたのだった。いつもは軽く感じている篭も少し重く感じる。しばらく外へは行かずに休養していた方がいいだろう。 「あ、花畑大丈夫かな」 あの嵐がこちらに来ていない事は周りの様子を見れば分かるのだが、それでもミキにとって花畑は自分の子供のようなものだ。無為な程に心配をして、なんやかやと理由をつけ顔を見たくなるのも仕方がない。 玄関に籠を置き、家の裏にある畑へ向かう。真円の月が頭上から明るく道を照らしていて舗装の無い砂利道も歩きやすかった。「あ」花畑が視界に入った時と同時にその存在に気付く。花畑の中央に立つ広葉樹の下、やや小柄な人物の影が見えた。近くに寄らずとも、影の形で誰かはすぐわかる。 「フリーダ!」 「やぁ、ミキくん、おかえり」 手を上げゆらゆらと振る幼馴染み。ミキが駆け寄ると、フリーダは嬉しそうにしながら立ち上がり 「この馬鹿者めっ!」 「ひにゃあ!?」 立ち上がりざまにミキへ体当たりを見舞った。突然の事に受け身をとれずミキはフリーダ共々倒れ伏し、ミキは目をぱちぱちと瞬く。 「な、なに?痛いよ、フリーダ。どうしたの?」 「どうしたって!?心配したんだぞ、ぼくは!帰ってくる日には帰ってこないし!ゲリーくんから帰ってきたって聞いたから待ってたのに、なかなか戻ってこないし!」 ミキに跨がったままのフリーダは顔をしかめ、ミキの胸を突き飛ばすように叩く。 「どうせあの子のとこ行ってたんだろ……っ」 「あ……うん、そうだよ」 「ッ、幼馴染みよりっ!友達より大事なんだ!?」 「え、違うよ!フリーダ!」 「知らない、アホ、バカ、こんなミキくんだったら嫌いになっちゃうよ!」 唇を震わせフリーダはミキを睨み付ける。目尻が光るのは浮かんだ涙を月が照らす為。「……泣いてるの?」不躾な問いにフリーダは目を見開き、それから慌てて顔を伏せた。 「あ、あの」 「……」 「ごめんなさい、泣かないで」 おそるおそるフリーダの頭を撫でる。出来るだけ優しく、子供を慰めるように。俯いたままのフリーダはされるがままで何も言わない。 「…………」 「心配してもらってるのが当たり前になってて、あ、忘れてたんじゃなくて、その……ごめんね、フリーダ、あの……」 「ごめん、ミキくん」 顔を上げたフリーダはやはり目を潤ませていたが、口角は上がっていた。「ぼくこそ、ごめんね」瞬きをひとつすると涙が珠になって落ち、ミキの服にじわりと染みた。 「大人げなかったよ、ぼくはきみのお姉さんなのに情けないや」 幼馴染みはそう言ってミキから降りて、隣に座り直す。ミキはどうしたらいいか分からず視線を泳がせていると、フリーダが笑う声を聞いた。「なんて顔してるのさ」頬を突つかれ、大柄な体躯に子供のような真白の心を持つ少年はキョトンと目を丸くした。 「怒ってない?」 「もう怒ってない。ミキくんも悪かったけど、ぼくも言い過ぎだったからオアイコ」 「……うん」 「寂しかったんだよ、ちょっと」 息を大きく吐いて、フリーダは弟分にもたれかかる。 「今までぼくが守ってたのに、気付いたらきみはひとりで何処かに行ってさ。ぼくの生活の一部だったきみが、きみだけの世界を作ってさ、ぼく置いてかれたって思った」 「フリーダ、俺は」 「言うな言うな。分かってるから」 くすくす笑って言葉を止める。だがミキは首を振った。 「置いてかないよ」 「ん」 「一緒にいるよ」 「うん、分かってる。知ってるよ、――大丈夫、全部分かってるからさ」 小柄な幼馴染みはそう言って、ミキの腕を抱き締めた。 それからミキは今回の旅を語り、フリーダは興味深げに聞いていた。やがて話が尽きた頃、ミキの腹の虫がけたたましく鳴いた為、二人は笑いながら家に帰る事にした。 前を歩く小柄な幼馴染みの背を見ながら、叶うなら彼女を連れて外へ行きたいと、いつだったか願った夢を思い出す。沢山の色を散りばめた花畑を見せてやりたい、きっと喜ぶだろう、彼女なら。そうだ、子供の時に彼女に花畑を――? 上手く思い出せない。 確か。 あれは。 暗い。 闇? そうだ、夜の闇にいた。 刺すような痛み。 誰かが泣いていた。 自分が? 彼女が? ……彼女? そうだ、彼女と約束したんだった。 約束? ――――なんの? 「フリーダ」 呼び掛けるとステップを踏むようにフリーダはくるりと振り向く。 「俺達が小さい時に何か約束したっけ?」 問えばフリーダは首を傾げ、それから 「したよ」 にっこり笑う。どんなものかと問う前に幼馴染みの少女はミキの手を取り、見上げて 「ぼくがミキくんを守るって」 微かな悲哀を混ぜた笑顔でフリーダは言った。  Back Back
|
||
 |
 |