 |
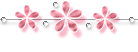 |
 |
|
今日は夕日と同じ色の花にした。去年、兄が3ヶ月に及ぶ採取の旅から帰って来た時に貰った種を育てたものだ。橙色をした小さな花が鈴なりになっており、鈴蘭と形は似ているが、花の大きさはそれより小さい。花の名を知りたくて調べてみたが載っていなかったので、とりあえず夕色の鈴と名付けておいた。 その夕色の鈴を数本束ね、薬を包む包装紙を巻いた花束。ミキは花束を持ち、陽光に照らされた道をゆっくりと歩く。 「今日、は……」 今日こそは。 「あの人にちゃんと渡すんだ」 花束を握る手に思わず力が入りくしゃりと紙が歪み、ミキは慌てて緩めた。 四ヶ月前、ミキは花屋の彼女に花を送った。といっても、人見知り激しい彼が勝手口に置いてきただけだが。なんとなくそうしただけで、そこに然程特別な想いはなかったはずだ。ただ彼の手には一束の花と、目の前に彼女の店があったから。 店を一所懸命に切り盛りする彼女を応援したいのと、それから―― よく分からない、ただただそうしたいと思ったのだ。時折馴染みの喫茶店で彼女の姿を見る事があったから親近感が湧いていたのかもしれない。 だが最初に花を贈った、その後からは確固たる意識をもって彼女に花を贈っていた。初めて彼女に贈った時に見た優しくて綺麗で柔らかな笑顔がまた見たい。そんな理由でミキは綺麗な花を手にいれると必ず彼女の店を訪れた。話す事も顔を合わす事もない。店が閉まる夕暮れ頃に勝手口にそっと花束を置いた。恥ずかしくて彼女が来るのを見届ける前に帰る事が多かったが、彼女の帰りを待つ事もあった。 「こんにちは、いや、えっと、はじめまして、の方がいいか……俺は……花が……いつもあなたが、あなたを?んーっと……――」 花屋に行く道すがら、ミキは何度も家で練習した自己紹介の言葉を口にしていた。 今日こそはきっと声を掛けてみせる。 声を掛けて、少し話をして――それからの事はよく考えていない。どういった反応が返るかを考えると怖くなるから止めておいた。ただ一度でいいから話をしてみたかったのだ。 花を贈り始めた頃は見ているだけでよかったのに、彼女を意識して見るようになってから、自分の内で花屋の彼女の存在が大きくなっていくのをミキには感じていた。 何をするにも何を見るにも、思考に彼女の影を見た。 空の青さに彼女の綺麗な水色の髪のことを、兄が飲むワインの紫に彼女の円らな紫の双眸を、綺麗な花を見れば彼女に送りたいと思い、夕焼けを見て彼女の店への道を急いだ。 フリーダは最初こそ呆れ気味に「そりゃもう、なんていうか――ちょっとした変質者だよ」と苦笑混じりに諌めていたが、「こうなったら話し掛けちゃいなよ」にんまりと笑って言い、今日は見送られてきた。途中までハンナが付いてきて、男は度胸だとか、やれば出来るだとか、花屋の彼女は優しいから心配しなくていいだとか。 「絶対大丈夫なの」 小さな友人はそう言ってミキを鼓舞してくれた。 「……大丈夫だよね」 ミキは何度も呟いて、一歩一歩を踏みしめて歩く。一歩一歩と彼女の店が近くになる。 最初は強張っていただけの体も、近付くにつれ歩幅が小さくなり、じわりと手のひらに汗を掻き始め、心臓が大きく跳ね上がり始め、彼女の店から少し離れた曲がり角で彼の足は完全に止まった。 ここを曲がってすぐ。 目的地まであと十数歩。 「う……」 足が動かない。心臓が早く逃げ帰れとばかりに早鐘を打つように跳ね回り、彼は胸元を抑えた。そして動くのを拒む足を無理矢理前へ。摺り足になりながらも一歩。更に小さくなった一歩で前へ、彼女のいる、その場所へ。 「わっ!」 角を曲がった瞬間、彼女の姿が見えた。 毛先を緩く巻いた青い髪には鬼灯色のリボン、白磁の肌に透き通った菖蒲色の目。宵闇色の上に撫子色を重ねた胸元が開いたワンピース、それから綿毛色のロングブーツ。じょうろで水をやる姿は一枚の絵のように美しくミキは思わず「綺麗だなぁ」と呟く。じょうろから流れた水の粒が陽光に反射してきらきらと。まるで彼女自身が輝いているように見えた。 じっと彼女を見つめた後、俯き自分の姿を鑑みる。 赤銅色の硬い髪、いつも何かを睨み付けているような金色の鋭い目、もうすぐ2メートルを越す筋肉質の体を黒い衣服が包む。顔はお世辞にもカッコいいや綺麗といったものではない。(悪役として見るなら前者は有り得るが、残念ながらミキに悪役をこなす度胸はない) その自分が彼女と並んだ姿を想像してミキは顔をしかめた。明らかに住む世界が違う。陽の光を浴びる鮮やかな世界にいるのが彼女、自分はその影。埃と油の匂いをさせた乾燥した世界にいる。 自分のいる場所は大好きだし、その場所で働く誇りもある。そこに住む人々は皆優しく気高い。だが、彼女の世界とはきっと混じり合いはしない。 ――ミキはかぶりを振った。 「駄目だよね、やっぱり」 彼女の姿をぼんやり見つめながらミキは苦笑する。風が一際強く吹いて彼の巨躯を覆っていた暗色の外套が広がった。目に砂が入りそうになって目をこする。 「帰ろう」 呟く。 帰って、それからこの花は店に飾れば良い。それから、もう来ない方がいいだろう。フリーダが言うように自分のしている事はあまり誉められたものではないから、彼女だってそろそろ不安になってきているかもしれない。 ――ただ怖じ気付いただけかもしれない。 もし断られたら?悲鳴をあげられたら?そもそも話など出来やしない。鮮やかな色彩の中にモノクロが入り込む隙間など何処にも用意されていない。 自分は自分のいるべき世界がある。 「……っ」 何がしたかったのだろうか、自分は。もやもやとした想いが胸を刺した。 「きっと……、そうだ、友達になりたかったんだ」 きりきり、ぐるぐる、もやもや、ずきずき。 もし心というものがあれば、それは胸にあって、それでどんな傷より一番酷く痛みを感じる場所に違いない。悲しいよりずっと悲しくて苦しくて、ミキは眉根を寄せ息を吐いた。舌がぴりぴりと痺れている気がする。 また風が強く吹いた。早く帰れと言われている気がしてミキは来た道に振り向く。だが 「あ、え!?」 その時、外套が引っ張られた。  Back Back
|
||
 |
 |