 |
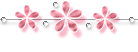 |
 |
|
魔王。 それがミキの二つ名だ。彼の外見がとある絵本で描かれている魔王の姿に似ている事から名付けられた。 乾いた血の色をした髪、全てを憎むかのような鋭い眼光を持つ金目、口からは太い牙が覗く。魔王が捩れた角を持つ代わりにミキには外側に反った猫の耳、魔王が顔に醜い傷痕がある代わりにミキには頬に朱色の紋様が片頬に二つずつ、魔王が太い蜥蜴のを持つ代わりにミキには毛足の長い猫の尾があった。魔王は大きな血塗れの鎌を持つがミキは何も持たない。――そんなもの必要がない。ミキに傷付けたい相手などいないのだ。彼はただただ人々の平和を願っている。 幼い頃、大病を患いろくに部屋から出ずにいたことがあった。病のせいで痩せ細り、青い顔をしてぼんやりと窓から外を眺める姿は同年代の子供達からは幽鬼のように感じられたと後から聞いた。彼がそんな姿になった理由を知らぬものには至極気味の悪いものだったらしく、ようやっと出歩けるようになった時、ミキは周囲から孤立していた。 その頃は今のように恐ろしげな容姿ではなく、どちらかといえば弱々しい雰囲気をまとった子であったから今のように忌避されるのではなく、排除の方向へと事態が流れた。つまるところ暴言、暴行といった弱者への苛めが行われたのだ。その事態は彼の数人の友人と、彼の兄によって打破されたが、その頃には彼の心には傷が深く穿たれていた。切り傷は治ろうとも、えぐられた傷は元には戻らない。彼の強い人見知りはこういった所から始まったのだと今でも兄は悔しげに言う。 そういった苛めを受けた彼だが、その心に相手を恨む気持ちは一切無い。そもそもそういった感情が欠如しているのかもしれないと彼の友人は苦い顔で言う。それは防衛本能によるものかもしれないが、おそらく彼を取り巻く環境にあるだろう、とも。 彼は過保護に育てられた。というのもミキが今の家族と血の繋がりがないからだ。俗にいう捨て子なのだ。泣く事しか出来ないような乳飲み子だった彼を当時12歳の兄が見つけたところからミキの生活が始まる。出発点がそういった悲観的なものであったから両親と兄は過剰に愛を注いでいた節がある。何かを嫉み、妬み、恨む隙が無い程にミキは愛され、満たされていたのである。 大病を患う前から度々病に伏す病弱な少年であったのも過保護に拍車をかけていた。今でこそ頑健ではあるが、当時は乾いた風が吹けば咳き込み、冷えた風が吹けばクシャミをして、体を冷やすと高熱で寝込む――といったような体の弱い子であり、その度、ミキは過剰だと子供ながらに思うほどの看護を受けた。兄などミキの為によく効く新薬を、と成人せぬ内から荒野に新種の薬草を探しに出た程だ。(兄が長旅に出るのはこれが発端で、以降趣味になっている) こういった理由が重なり、彼は心優しい青年へと育った。姿こそ恐ろしいものになったが、彼の心は常に暖かい。家族を愛し、友を愛し、綺麗なものを愛し、なにより世界を愛している。 「ミキ兄は、まおうみたいな顔だよね」 世話をしている花畑で静かに過ごすミキに子供はおかしそうに言った。 「でもミキ兄ちゃんは優しいから魔王にはなれないね」 「でもまおうみたいだよ」 「でも誰も傷つけたりしないよ。こないだなんか街に入り込んでたネズミからぼくを助けてくれたんだぜ」 「じゃあ、ええっと、守るまおー?」 「あら、花畑の主に魔王なんて似合わないわよ」 「じゃあ、じゃあ、えっと、なにまおうがいい?」 「魔王から離れたらどうかしら……」 「あっ、そうだ!じゃあ間を取って花守魔王にしようぜ」 「はなもりまおー!」 くるくるとミキの周りを走り回るミキの小さな友人。魔王という言葉は人聞きは悪いとは思ったのだが、なんとなくミキも楽しかった。 だれも傷つけない魔王様 恐くて優しい心の魔王様 でも少し怖がりな魔王様 魔王様は怒らない 魔王様は泣かない 魔王様はやさしい だって全部持ってるから みんなが欲しがるのものを みんな魔王様にあげるからさ 魔王様もみんなにあげるんだよ でも ちょっとだけ欲しくなった きっときっと無理だけど だってだって遠くて遠い だけどだけどって魔王様 ほんのちょっぴり ちっちゃな勇気で ある日 太陽に手を伸ばした ミキ・マタ・オリは年齢以上に育った外見とは反対に中身はまるきり子供である。さすがに玩具にはしゃぎはしないが(喜びはする)子供の好む物の多くを彼は好む。菓子は最たるもので彼の部屋には何かしらの菓子が常備されている。たとえ自分の事であっても必要に迫られなければ店の外に出ない出不精の彼だが、菓子にかけてはその限りではない。菓子を買う為に唯一自分の為に外へ出掛ける。 とはいっても彼は臆病で人見知りが激しい為、自然と行き慣れた店へと足が向かう。新しく出来た店など行きたくて仕方がないのだが客があまりにも多いとタタラを踏んで結局行けずじまいだ。その時は友人達に頼むのだが、やはりショーケースの中を自分の目で確かめ、よく吟味して決めたいと思う。今まで出来た試しがないが。 しかし人気店の菓子はやはり美味い。食べ飽きない。もう一度、いや何度でも食べたいと思うのだが、それを友人に頼む訳にはいかない。かといって彼に勇気は無い。 「自分で作るしかないんだよなぁ」 独り言りながらミキは裏通りの飲食店街を歩いていた。空には、頂点より少し傾き、けれど輝きを衰えさせない太陽がある。時刻は三時過ぎ。昼食の時間を過ぎた為どの店も空いており、歩きながら中を覗けば店員がお茶を啜って休んでいた。 ミキは菓子作りが趣味である。趣味というには頻度が高いが。菓子店に通えない彼は自分で作ることを思い付き、5年前からそれを始めた。今ではある程度のものは作れるし、焼き菓子に至っては味見係の子供達からの評判も高くミキも自信を持っている。彼の家から甘い香りが漂ってくると、子供達はこぞって味見――という名の暴食――にやってきた。 本を頼りにした見よう見真似で始まり、馴染みのパン屋に暇を見ては質問に行き、また各店の味を確かめ、少しずつ改良を加えてきた。なんとか自分が納得のいく味にはなったのだが、やはり本職には全く敵わない。結局、ミキは喫茶店やケーキ屋へ赴くしかないのである。 今も喫茶店へと向かっているところだ。幼い頃に兄に連れられて来て、兄が長旅に出ている間も足繁く訪れている。客入りは然程でもないのだが本業は細工師で、喫茶店は趣味でやっている為問題はないらしい。だが趣味にしておくには勿体無い程、何においても美味い。珈琲から始まり軽食、ケーキまで非の打ち所がないとミキは思っている。 「……やっと着いた!」 問題は少し遠いこと。ミキは嘆息を吐き、見慣れたその場所をまじまじと見つめる。 屋根は落ち着いた朱金色。そこから伸びた灰色の煙突から白い煙が現れては青空に霞んでいく。壁は若干薄灰色に汚れた漆喰。道に面して多く取り付けられた窓の数枚はステンドグラスになっており、向かって右から左へ太陽が上る様を表している。上部に磨りガラスを嵌めた木製の扉はニスでピカピカに光っていた。 ミキは扉にかかる営業中と乱雑な字で書かれた札を確かめると、ノブを回し、ゆっくりと押し開く。途端香ばしい珈琲の香りが溢れて、ミキはほぅと息を吐いた。この香りだけでもう満たされた気分になる。 ミキは自分が入れるだけの隙間を開けると決して大きくはないその店へ足を踏み入れた。カウンターで神妙な顔で本を読んでいた店主に声をかけると、店主は本から視線を上げないまま「おう、座って待っておけや」言って手を振る。幼い頃からの知り合いの為、ミキも店主も慣れたものである。ミキは返事を返し、いつも座っている一番奥の席へと進む。 店内は一言で言うなら乱雑。または節操が無い。店主のその時の気分によって買い集められたものが所狭しと置かれている。窓際に並べられたのは色鮮やかなとんぼ玉、その隣には大小様々な花瓶。壁に取り付けられた本棚には古文書じみた呪文書もあれば子供の命名辞典、果ては「メイドさんと頑張る!お金が溜まる本」といった珍妙な本までが一緒に詰め込まれていた。 ミキが今座っているテーブルセットも含め、店内に置かれた机と椅子も店主が市場で気に入り買ってきたもの。骨董的な重厚なものもあれば、実用性重視のもの、何処に座るか分からない椅子と物が置けそうにない傾いた机、子供用のものもあれば、かつて王が使っていたという眉唾の逸品も存在する。その中でもミキは最奥に置かれた大きめの椅子を好んで座った。細かな意匠の凝らされたそれが好きなのもあったが、何より普通より体が大きい彼の体にちょうどいいサイズだったからだ。 ミキはいつもの椅子に着き店主を待った。店主は非常にマイペースで客が座った後でもなかなか注文を取りに来ない。ここへ来る客は常連が殆どであるし、注意をしたところで彼の遺伝子に刻まれた習癖を治せるはずがない。それもまたこの店の一部だと、ミキは待つ時間も楽しむことにしている。ジャンル分けされていない本棚から面白そうな本を見つけたり、窓から裏通りを歩くネコ達を眺めたり、ただぼんやりして店内を眺めているだけでも楽しかった。 今日は何をしようかと視線を漂わせていると「うおあっ!!!」カウンターから店主の野太い悲鳴が聞こえた。急いでミキが駆け寄ると 「くっそ、びっちゃびちゃだ」 本を読みながら、ピッチャーの水をグラスに注ごうとしたらしい。片手に本を持ったままの店主は空のグラスを中心に水浸しになったカウンターを嘆息しながら見つめていた。 「うぉい、ミキ、そこに布巾あっから取ってくれ」 「ん」 手を伸ばしカウンター端に置かれた、乾いてバリバリになった布巾を数枚取る。一枚を店主に渡し、ミキは余った布巾を水の上に被せた。瞬く間に布巾は水気を湛え、目一杯吸わせた布巾をあらかじめ店主が用意していたバケツの上で絞った。 「手伝わせてわっりぃな。今日もケーキ食いに来たんだろ?一個オマケしてやっから、好きなん選んで待ってろ。おいらはコイツを片付けて、あー、ズボンまで水いってっから着替えるわ」 「あ、俺は別に」 「おいおい、ガキが遠慮すんなぃ。作ってんのは嫁さんだがな、あいつも同じ事言うだろうさ」 「そっか……。ありがとう、いただきます」 ミキはにっこり笑い、もう一枚乾いた布巾を取りカウンターに残る水気を拭く。店主はもう一度礼を言うと本をカウンターの端に置き、バケツを手に奥へと入っていった。奥には住居兼、本業の細工師の仕事場があるのだ。 ミキは粗方水が取れると暫し考え、そのままカウンターを拭く事にした。ちょうどいい湿り気もあるし、暇であるし、すぐ終わる事だ。それが気付かれなくても誰かの為に何かを為すのがミキは楽しかった。 やがてそれも終わって手持ちぶさたになると、言われた通りケーキを選ぶことにした。店の中ほどにあるショーケースには数種のケーキが入っている。その前で少し前屈みになって中を覗き込む。 最初に目に付いたのは鮮やかなフルーツタルト。星イチゴをベースにベリー系を散らしたそれは店で一番人気のものだ。ベリーの刺激的な酸味と星イチゴの甘さが口の中で合わさり、そこへ更に添えられた生クリームが優しく蕩けさせる。その隣にはチーズタルト。正式名称は長いものらしいが此処ではチーズタルト、またはチーズケーキで通っている。濃厚なクリームチーズを滑らかに練り上げ、そこへレーズンを混ぜたものを成形されたタルト生地に注ぎじんわり焼いたものだ。彩りには劣るものの一口、口に運べば濃厚でいて甘すぎないチーズ生地と甘く香しいレーズンが舌を喜ばせる。また、その隣にはお馴染みのイチゴのショートケーキがある。基本ゆえ難関。個人によって特色が変わるそれを、この店は軽くしあげている。若干柔らかすぎかと思うほどの生クリーム、一つだけ乗せられたイチゴ。これは甘味の際立つ星イチゴではなく普通の物。しかしサンドしたイチゴは星イチゴにし、甘さと酸味を調和させている。スポンジはしっとり柔らかいシフォンケーキに似た生地を使っており、全てが相まって後味がさっぱりした風味となっている。下段にはガトーショコラ、ティラミス、それからマタタビ酒のパウンドケーキと書かれた札の付いた空のトレイ。どうやらパウンドケーキは売りきれたらしい。 ティラミスはチーズタルトと同じく上質のクリームチーズを使っている。そこに自家製のカッテージチーズを足し、風味にオレンジピールを刻んだものを混ぜ合わせたチーズ生地、それを店のオリジナルブレンドのコーヒーを染み込ませたビスケットの上にたっぷり乗せた物だ。チーズ生地の上に甘さを控えた生クリームを重ね、甘味のない純正ココアを振りかけたそれをミキは好んでいる。 それから 「ガトーショコラだ……」 名前は知っているし、おおよその味もわかるが、この店では初めて見る品だ。焦げ茶色のどっしりした生地に軽く粉砂糖をかけたそれを見つめミキは首を傾げる。 今日はチーズタルトにしようと思ったのだが、こちらも気になる。 「二つにしようかな」 呟いて、二つを見比べる。しかしティラミスを捨てがたくもあり、ミキはケースの前で低く唸る。そこへ 「ん?」 扉を開く軋み、明るい日差し。そちらをに顔を向けると……――思わず唸り声が洩れた。 扉を開いたその相手は、つい最近、友人――という程の仲ではないとミキは思っているが――になったばかりの女性。ミキが花を送り続けた花屋の店主、メレディス・アイメルトだった。 二人は暫く互いを見つめ、最初に視線を外したのはミキ。そして 「ミキさん」 声をかけたのは彼女から。扉をピタリと閉め、早足にミキの隣に並ぶ。 「こんにちは」 「……、あ……」 ただの挨拶も上手く返せない。体が強張り(前屈みだった体は彼女を見た瞬間に棒のようにぴんと直立になった)早くも手はじとりと汗をかき始めている。 初めて彼女に花を手渡してからミキは花を贈っていたが、あれから一度も彼女に手渡しで贈っていない。前と同じように勝手口の石段に置くだけ。 結局ミキは挨拶を返せなかった。だがメレディスは気にしていないのかショーケースをにこにこと覗いている。 「こちらには、よくいらっしゃるんですか」 ミキを見上げながらメレディスは問う。ミキは何とか首を振って肯定すれば「そうですか」彼女は少し考え 「でしたら、ここへ来ればミキさんに会えるんですね」 「……ぁ、あぁ。――たぶん」 ミキは言葉を濁す。 彼女の言葉はひとつひとつが意味深で、というよりもミキにはイマイチ理解出来ず反応に困ってしまう。それはどういう意味なのかと問いたくもあるが、彼にそんな度胸はない。 よかった、と笑うメレディスは再びケーキを眺める。その横顔をじっと見つめていると、奥から店主が帰ってきた。二人が並んでいるのを見つけると「へぇ……?」にやりと口角を引き上げる。 「ぃよう、嬢ちゃん。あー、んん、確か――メレディ……オ?」 店主はミキの隣に並ぶメレディスを見つめ、首をかしげる。メレディスはくすくすと笑いながら「ス、ですよ」訂正する。 「あぁ、悪い、メレディス嬢ちゃんね、ふふん」 言いながらカウンターに入る店主。何がおかしいのか笑みは湛えたまま二人を交互に眺めている。メレディスはショーケースに目を戻していたので、ミキは店主に首をかしげてみせて、どうしたのかと問うてみた。だが帰ってきたのは右手で小指を立てた妙な合図。 「……」 その意味が分からずミキは顔をしかめる。途端吹き出し笑い始める店主。と、同時にメレディスが「あの……」ミキに声をかけた。 「ミキさんはどれにするんですか?」 「え……」 向き直り首を捻る。暫し考え、チーズタルトを指差す。するとメレディスは「あ、同じですね」目を丸くして、それから微笑んだ。 「ガトーショコラもティラミスも美味しそうで――……まだ食べた事がないし、どうしようかな」 二つを見つめメレディスが言う。同じくミキもショーケースの中を覗く。 「ん、やっぱりチーズタルトにします」 「あいよ、飲むもんはどうする?」 「前に頂いた紅茶ありますか?」 「んん、あれね、わかった。じゃ、席で待っとけ。で、ミキ、おまえは」 だが、ミキは視線を泳がせ答えない。「ミぃキぃぃ?おら、聞いてっかよ」「き、聞こえてる……」俯き、低い声で。 メレディスはまだ席につかず、隣でミキをにこにこと見つめていた。 逡巡ののち、ミキは店主に近づくと微かな声でガトーショコラとティラミスの二つを頼む。その二つは言わずもがなメレディスが言っていたもので、また自分が悩んだもの。自分が頼み、それを分ければ彼女が喜ぶのではないか、そもそもミキは量が欲しいのではないからそうする事に問題は無い。 「ほほぉ、なっるほどぅ……?」 キシキシと風変わりな笑い声をあげ店主はカウンターの奥へ戻っていく。ミキはその背中を見つめ目を瞬いていたが、彼が全くこちらに振り向かないので諦めて席へ戻る事にした。 「……」 カウンターの奥にいる店主を不思議そうに見つめるメレディスの横を通り抜け、先程の席へと急ぐ。 「あの、ミキさん?」 後ろから声。振り向けば、変わらず微笑んだままのメレディス。ミキは息を吐き、じぃ、と花屋の彼女を見つめる。あぁ、今日も綺麗だな、その格好で寒くはないだろうか、花屋は休みなのだろうか、なんて、ぼんやり考えて―― 「ご一緒していいですか」 「え」 「駄目ですか?」 「あ」 「………」 「………」 緊張と恥ずかしさにミキの尻尾が膨らむのと、店主が笑い声をあげるのは同時だった。 彼が断れるはずもなく(そもそも断る理由もないが)ミキの前には、不釣り合いな大きさの椅子にちょこんと座るメレディスがいる。 ミキは視線を机に向けたままあげられずにいた。気を落ち着かせられないものかと机の木目を視線で辿る行為を続けているのだが、胸の鐘は一向に大人しくならない。 こうやって対面で喫茶店にいるのだから何かしら会話があった方がいいのだろうとミキは考える。友人と来た時は他愛もない話でゆったりと過ごすのに、今は明らかに緊張の時間だ。 ……否、そう感じているのは自分だけだろう。 ミキは小さくかぶりを振る。 前に一度彼女の店で紅茶を煎れて貰った時もやはり無言の時間が多く、ミキは始終肩を強張らせたままだった。しかし彼女は決して緊張しているようには見えず始終笑顔だった。別れる間際、一瞬だけ影を見せた気がしたが。 「……――」 何か話題はあるだろうか。先程の彼女の言葉振りなら再びこの場所で顔を合わす事はあるし、自分は、たぶん、彼女と仲良くなりたいのだ。 話題、そうだ、花の事や、あぁ、それからケーキの事だ。有難いことに話題に欠くという事はないらしい。 息を吸う、吐く、体に力を込めて――……顔をあげ 「あの」 「あの」 声が重なる。メレディスがこちらを見て首をかしげた。 「ミキさんからどうぞ」 「あっ、……あぁ、うん」 綿毛のような笑みをするひとだとミキはメレディスを見つめる。真っ白で柔らかくて、けれど酷くぼやけた笑み。今は楽しくて笑っているのではないだろうし、何かが嬉しいのでもないだろう。 どうして彼女は何もないのに微笑んでいるのだろう? 「ミキさん?どうかしましたか?」 「……いや」 首を振る。 気にしすぎだ。これが彼女のスタイルで、それをとやかく言うような立場ではないし、彼女がそれを望んでそうなっているのなら尚更気にしない方がいい。 ミキは息を吐き、思考を切り替える。 暫し考え、最初は無難な話を切り出す事にする。メレディスからの話も気になりはするが先を譲られたのだから自分から話すことにする。 「……ここ、何度目……?」 われながら無愛想な口調だとミキは思う。 だが他人と話すのが苦手なミキにとってこれが精一杯なのだ。緊張が声帯まで及び上手く声が出ないのである。 それに話している間に何を言えばいいか分からなくなって混乱してしまうのだから極力言葉少なくして話した方がいいのだ、というのが強面薬屋の主張。友人たちは屁理屈だと言って嘆息を付くが、彼とて好きでこうなっているのではない。本当なら誰とでも親しく話せるようになりたい。そうすれば友人も多く出来るし、きっと世界は広がるだろうから。 メレディスに対してもそうだ。もし叶うなら、もっと普通に、緊張せずに話したい。そうすれば花の事も菓子の事も十分に話せるのに。 その日が来るかは分からないが、もし叶うとしても遠い遠い未来の事だ。 ぼんやり青い髪の花屋を見つめたまま遠い未来の事を思い浮かべようとして、全く思いつかなかった。やはり彼女と自分は世界が違うのだろう。 「ええと、3回目ですね」 メレディスが言う。 「最初はお客さんに教えてもらって、一緒に来た時にショートケーキを食べて、それが凄く美味しくて」 だからもう一度、今度は一人で来たのだと彼女は笑った。 「その時に頂いた紅茶も凄く美味しかったから、また来たんです。そうしたらミキさんがいるから驚きました」 「……同じ。会うと思わなかった」 「ふふ、嬉しい偶然ですね」 メレディスの笑みが深まり、ミキは気恥ずかしくなって俯く。 「偶然は必然だって言うぜ、若人よ」 野太い声と共に現れたのは大きめのトレイを持った店主。トレイからティーポットを二つ、二人の間に起き、次いで藍色のカップとソーサーを並べる。最後に砂時計を逆さにして「これ全部落ちたら淹れろよ」言って、ケーキを取ってくると戻って行く。 「……この紅茶が……?」 「はい、香りがそんなに強くなくてケーキに合ってるんです。それだけだと少し物足りないかもしれませんが、何かと一緒だと上手く際立ててくれるというか」 「……そう」 「普通に売っているものとは全然違う感じで」 「……――うん」 「おう、若人。お話の最中失礼すっぜ」 戻ってきた店主の手にはティーセットと同じ柄の皿。そこには二人が注文したケーキが置かれている。 「ではごゆっくりどうぞ、ってか」 皿をそれぞれ二人の前に置き、皿の上にフォークを置くと店主は仰々しく礼を取る。 「……ありがとう」 「ありがとうございます」 「おいらはあっちで本読んでっから、用事あったら呼びな」 何故か去り際にミキの肩をぽんぽんと叩き、にんまりと意地の悪そうな笑みを浮かべる。何かを呟いたらしく口元が動いていたが、ミキの耳には聞こえなかった。 「ミキさん2つなんですね」 「あ、あぁ……これは」 自分の前に置かれたケーキ皿をメレディスの方へと押し出す。「え?」メレディスは困惑の体でミキを見つめるが「好きなだけ食べていい」ミキはそう言って、砂時計へと目を移した。全てが落ちきるまで少しといった所だろうか。砂時計のガラスに店内の光が鈍く映っている。 「あ、あのっ!」 「……」 焦りの混じったメレディスの声で、視線を前へと戻す。その顔にはやはり困惑が見えた。 「えっと、これは……?」 「食べた事がないって言っていなかった、か?……だから」 食べていいと皿をもう一度メレディスへと押す。 「あの、もしかしてわたしの為に二つを取ったんですか?」 その問にミキは首を振る。 彼女の為かといえばそうかもしれないが、自分が食べたかったものでもあるので否とも言えたからだ。強いていうなら 「美味しいから、食べて欲しい」 彼女にこのケーキの美味しさを知って欲しかったから、だろうか。(ガトーショコラは分からないが、この店なら安心して味わえるはずだ) メレディスは暫しキョトンと目を丸くした後「ありがとうございます」クスリと笑う。 「じゃあ少しだけ頂きますね」 そう言って一口分を自分の皿に分け「それから」メレディスは自分の皿にあるチーズケーキから少し大きめに切り分けミキの皿へと乗せた。 「……あっ」 「貰ってばかりはいけませんから、ね?」 ミキの前へと皿を返し、彼女は目を細めた。ミキは暫らく戻された皿を見つめていたが、渋々と頷いてみせた。別にチーズケーキを分けて欲しいからと彼女にあげたのではない。 ミキがふと顔をあげると、ちょうど彼女がティラミスを口にする所だった。口に含んだ途端少し驚いた顔をして、それから嬉しそうに口元を緩ませる。 「おいしいです、とっても」 幸せそうな顔で彼女がミキへと笑いかける。 「……、まあいいか」 彼女が喜んでくれるならそれでいい。口元を覆う外套の中で小さく呟き、ミキは皿に置かれたフォークを手に取った。 「……」 「……」 ケーキが運ばれてから会話は無かった。 かちゃりかちゃりとフォークが皿を叩く音と店主が本をめくる音だけが店内に響く。最初はそれが妙に怖かったが、暫くするとそれに安心感を覚えた。前の時も同じだったはずだが、今回は馴染みの場所であるし、好きなケーキを前にしているせいで落ち着いてきたのだろう。 「……ごちそうさま」 「ごちそうさまでした」 全てを平らげてしまうのは二人同時だったらしく、ミキが顔をあげた時にメレディスと目が合った。慌てて目を逸らすと「ミキさんって恥ずかしがりやさんなんですね」とのんびりした声でメレディスは言う。 「すまない」 低く唸るようにミキは言って顔を伏せた。 「あまりひとと話す事がない。……だから何を話せばいいか……――、うまく、話せない。すまない」 「大丈夫ですよ、謝らないでください。わたしもまだ緊張していますし」 「…………、そうか」 ほぅと息を吐く。少し冷めた紅茶に手に取り一口含み、少しだけ視線を彼女へ向けた。 「……どうだった、ケーキ」 両手でカップを持ったまま、ぽつり、ミキは言う。 「はい、ミキさんに頂いたものも凄く美味しかったです。今度頼んでみようと思いました」 メレディスは空になったケーキ皿を眺め、それからミキと同じように紅茶を手に取る。 「ティラミスはあまり食べた事がなかったので、凄く新鮮で」 「……、作らないのか?……自分で作ると、思っていた」 「ティラミスは作った事がないんです。一度作ってみたいとは思っているのですが」 「……そうか」 ティラミスはその見た目から作るのに手間取りそうに見えるが構造は至って簡単でmミキもよく作る菓子のひとつだ。ただバットやカップに入れて冷やす為、保冷庫の場所を広く取ってしまうのが難かもしれない。おそらく彼女もそこを敬遠しての事なのだろう。ミキには旅先で採取したものを傷めない為に小型の氷冷魔法をかけた保冷庫を持っており、これを利用してゼリーやババロアなどを冷やしておく。 「よければ」 なんて事はない提案だ。彼女が喜んでくれるなら、と至って単純な思考 「今度作らないか。……いっしょに」 「ふぇ?」 「紅茶の葉も持っていく」 「え?え?」 彼女が気に入っているといった紅茶。それはミキが自ら葉を揃え、何年もかけて組み合わせた紅茶だ。殆どは近所のネコたちにしか売らないものだが、ミキが通うこの店にだけ卸している。店主が気に入っているのは知っていたが、実際の客の声を聞くのは嬉しかった。 だから少し浮かれていたのだろう。 「今度、店へ行ってもいいか?」 そんな事を口走った自分を呪ったのは、その日の晩の事。  Back Back
|
||
 |
 |