 |
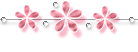 |
 |
|
朝から雨がしとしと降っている。採取へ出ようと思っていたんだけど明日に延期にして店番をする事にした。あまり強い雨じゃないけど、雨の日に外へ出たがる人は多くないから今日の店番は凄く暇だ。……いつも忙しいかっていうと、全然そんなことないんだけど。 フリーダに図書館から借りてきてもらった医学書を閉じ、冷えきった紅茶を飲み干す。 薬屋は薬だけ知っていればいいなんて事はなくて、ある程度は病や体についての知識も必要だ(場合によっては魔法も)。だから、たまに医学書を借りて大事そうな箇所をメモしておく。理解出来る所もあるけど、よくわからない所がほとんど。父さんに聞けば教えてくれるけど、考える事、調べる事は大事なんだってあまりいい顔はしない。 「ふぅ」 俺は嘆息を吐いて医学書を脇に寄せた。次いで色褪せた薬学書を手繰り寄せて無作為に開く。何度も読み返したそれをぱらぱらとめくり―― 「はぁ」 もう一度溜め息。雨のじとりとした空気や薄暗さはどうにも気を滅入らせてしまって、本に記された言葉が全く頭に入ってこない。空になったカップにポットから紅茶を注ぐ。時間の立ちすぎで濃く出すぎた紅茶、それを一気にあおった。それで頭をすっきりさせようとしたんだけど、ただ苦くて渋くて不味い思いをしただけだった。 少し噎せながらカップとポットを両手に持ってキッチンへ向かう。今日の朝に淹れたお茶が保冷庫にあるから、あれを氷を沢山入れて飲むことにしよう。 「むぃ」 「父さん」 居間で父さんが何か書き物をしている。覗き込んでみたけど、難しい単語が並んでてよく分からなかった。 「それなぁに?」 「むぃ、む。ももぃ」 「学会?そんなのあるの?」 「うぃ、も、いあいぁ」 最近出来たらしい。 「むぅ、ぃ、ぃりゅ?」 「大丈夫、ちょっと勉強し過ぎて疲れただけ」 「も」 「お茶でも飲んで休むよ」 言って俺は父さんに手を振りキッチンへと向かう。桶に張った水を手桶に移し、それで簡単にティーセットを洗う。ポットとカップは水切りのザルに入れ、そのザルから乾いたグラスを取り出す。 「もぃ!」 居間から父さんの声がした。 「はーい、一緒に入れるから待ってて!」 たまに父さんと、あと母さんを見て驚く人がいる。子供の頃は普通だと思っていたけど、父さんと母さんは普通のネコとは違う。 まず見た目。多種多様な姿のネコがいるけど父さんと母さんは別格。 違う世界に人間と猫っていうのがいるらしいんだけど、この世界にいるひと、つまりネコ達の原型は、あっちの世界の猫がこちらで住む時に活動しやすいようにって、人間みたいな姿を変化したのが始まりらしい。だいぶ減ったけど今でも違う世界からやってくるんだって。 で、父さんと母さんはたぶん猫寄りの姿なのだと思う。もこもこふわふわの長い髪。父さんにはもじゃもじゃのお髭もある。それから背は低くて3歳くらいの子供くらいしかなくて、ずんぐりむっくり。母さんには左右にぴんと伸びた猫の髭。 言葉の方も独特で、こちらは猫とも人間とも違って、兄ちゃんと俺と、あと近所の仲の良い人にしか分からない。言葉、というより声のニュアンスと響きで意味を成していて 「めぅめぅ、も、らーぃあ」 「えぅえぅ、ふ、あーひあ」 二つとも凄く疲れたって意味になる。 昔は普通の言葉を話す、普通のネコだったらしいんだけど、俺が物心付く頃には今の姿だった。どうして今みたいになったのかは色々と近所の人が言っているんだけどね。 曰く成長すると自然とああなる種族ではないのか。 曰く新薬の副作用ではないのか。 曰く呪いではないのか。 曰く実験ではないのか。 と、まぁ、全部眉唾物の話ばかりだけど当の二人は我関せず、事実を話すことはしない。聞いても、知らなくていいってプイって顔を背ける。 「兄ちゃんも知らないらしいし」 言いながら保冷庫を開け、作り置きの紅茶を入れたガラスビンを取り出す。半分ほど二つのグラスに注ぎ、ビンを元の場所にに仕舞ったら隣の冷凍庫を開ける。中から砕いた氷の幾つかをグラスに入れておしまい。尻尾で扉を閉めて、グラスを両手に居間へと向かう。 「父さん、持ってきたよ」 「んー」 父さんは一心不乱に紙に何かを書いている。声をかけると一瞬だけ顔をあげて尻尾を振った。置いておけって事なんだろう、紙を濡らさないように机の端の方においた。 「みぁ」 「ん?なぁに?」 居間を出ようとする俺に父さんが声をかけた。振り向くと、父さんが一本の花を持ってこちらへ歩いてくるところだった。父さんはその花を「む」俺に差し出す。 「いいの?」 「い。えむ、ぅるく」 「うん」 「あ、みー、うーしゅ、みぁ」 「そっか、ありがとう!」 差し出された一輪の花を、少し屈んで受けとる。 「みみ!」 「うん、頑張ってね」 ぱたぱたと尻尾をふりふり机に戻っていく背中に手を振り、俺も店番に戻るべく歩き出す。 「綺麗だな」 薔薇みたいだけど、それよりだいぶ小さな朱色の花と小さな丸い葉っぱ。長めに切られた茎を優しく摘まみ、鼻先へと持っていく。甘いのに、すこしすっとする香りがした。 父さんが言うには、この花は新種の物なんだって。香りにはリラックス効果があるし、他の薬と混ぜてやると効果を引き上げるんだそうだ。これを学会に発表するのにデッサンを取ってたんだけど、それが終わったから俺にくれたって訳。(畑で増やしてあるから一輪くらいあげたって、どうってことはないって言ってた) 花を見ながら思い出すのは彼女、メレディスさんの事だ。これをあげたら喜んでくれるかな、なんてカウンターに入りながら思う。 彼女と初めて会ったのは数ヵ月前で、話したのはつい最近。俺は彼女が好きだ。彼女が笑っていると嬉しくて嬉しくてしょうがなくなる。胸の辺りがふわふわして、肩も軽くなる。やっぱり誰かに喜んでもらえるのは気分が良いものなのだ。 「疲れてないかい?」 奥の廊下から声。振り向くと兄ちゃんが心配そうな顔でこちらを見ていた。 「朝から座りっぱなしでしょ?ちょっと休みなよ。店番はボクがするからさ」 「でも兄ちゃん、昨日帰ってきたばかりじゃない。ちゃんと休まなきゃ」 兄ちゃんは荒野の遠くまで採取に出掛ける為、2、3カ月くらい帰ってこない。一週間くらいしたらまた出ていってしまうから、ゆっくり休んでほしい。だけど兄ちゃんは俺を無理矢理席から立たせ 「其処で座ってるのも、中で座ってるのも変わらないよ。ん、もしかして兄ちゃんに任せるのが不安かな?」 なんて言って、俺の頭を撫でて笑う。 店番を任せるのが不安なんて事はないんだ。俺は口下手だし、顔だって怖いから、話上手で綺麗な顔した兄ちゃんの方が店番としては良いのだ。俺が返答に困っていると苦笑して「悩まないでよ、ただの兄ちゃんの優しさだよ」とポケットから飴を出して握らせてくれる。 「それに店の事任せっぱなしだからね、これくらいはやりたいのさ」 かくして俺の今日の予定は空白になった。 さて、どうしたものかと考えて――ううん、考える事もなく予定は決まっている。 手に持ったこの可愛い花を、あの人にあげよう。 兄ちゃんに出掛けると伝えると、雨なのに、と渋い顔をされた。すぐ帰るよといえば、やっぱり眉間にぎゅっと皺を寄せたまま「早く帰ってくるんだよ」と言う。それに頷き、俺は傘を片手に家を出た。 雨は細かくて、傘の下から手を伸ばすと柔らかく手を塗らした。道は少しぬかるんでいるけど、歩きにくいって程じゃないかな。転ばないように、でも早足で、いつもの道を歩く。そういえば雨の日に行った事がなかったかも……。 裏通りから出て、あのひとの店がある東通へ。雨の日はいつもよりひとが少ないから歩きやすかった。 「あ」 石畳を歩くネコ達を見て小さく声をあげる。いつの間にか雨が止んでしまっていたらしく、誰も傘を差していない。慌てて傘を閉じた。傘の先っぽで石畳を叩いて、雨粒を軽く落とし、紐で軽く縛っておいた。これで迷惑はないだろう。 片手に持った一輪の花を見やると、「うん」とひとつ頷く。もう少しで会えるのだと思うと嬉しいような、困ったような気分だった。 今日は包装もしていない、たった一輪の花だから、不思議に思われたりしないかと不安になる心と、跳ねるように動き始めた心臓とをおさえながら、俺は彼女の店へ早足になって向かう。 彼女は、雨が止んだせいだろう、中から花を入れた筒を出している所だった。慣れている感じだったけど、彼女は見るからに力が強そうではない。小走りで寄って、手に持っていた筒を持ち上げた。結構重かった。 一瞬きょとんとした彼女は俺に気付くと、ふいに笑顔を浮かべる。……やっぱり綺麗な人だなぁ。 俺は「手伝う」とだけ言い、筒を適当な場所へ置いた。「大丈夫ですよ」なんて、わたわたと慌てて彼女が言うけど聞こえないフリで中から花を入れた箱や筒を出していく。半分も出してしまうと彼女も諦めたらしく 「ありがとうございます、すごく助かります」 やっぱりここでも笑って、俺が外に適当に並べたものを綺麗に並べ始めた。ほんの数分後には全部いつもの通り。彼女の花の家が出来上がった。 「……あ、の」 「はい」 当初の目的を忘れている訳じゃない。胸のポケットにいれておいた花を取り出した。 「今日はこれだけ、で……」 彼女は別段背が低い訳じゃないけど、俺は少し屈んで花を差し出す。彼女は嬉しそうに笑って受け取ってくれた。 「可愛いお花ですね。見た事無い……」 「あ、……たぶんみんな知らない。……父さんが見つけた、新しい花」 「そんな珍しい花を……?えと、大丈夫ですか?」 「まだ沢山ある。……あ、あなたに見て欲しかったから持って来た」 「……」 「…………気に入らなかった、か」 「いいえ、とても嬉しくて」 そう言って、彼女は近くにあった空っぽの花瓶に花を差した。そのまま彼女の目は花を見つめたまま。 「ミキさんはやはりわたしの知らない世界を知っていますね」 「……いや」 「知りたくても知れない場所。すごく羨ましい」 微かに笑う。なんかちょっと悲しい感じがする笑い方。初めて会った時空を見ながら言った時の彼女と同じような空気。あの時は何も出来なかった。あの場はそれでよかった――なんて思ってない。誤魔化すように笑った彼女にかける言葉が出てこなかっただけ。 俺は彼女が好きだ。笑顔が好きなんだ。でも悲しい笑顔は嫌だ。 だから俺はとっさに 「いつか一緒に外へ出よう」 そんな言葉を言った。 ……しまった。こんな唐突な、しかも大して仲の良い相手でもない奴から誘いだ、怖がられるに決まっている。思った通り、彼女は目を丸くして、長いまつげに縁取られた紫色の目で俺をまじまじと見つめる。そこに浮かぶ表情は驚きか嫌悪かを確かめる前に、恥ずかしさで俯いてしまった。やがて聞こえた微かに笑う声。 「いいですね、外」 「……」 「行きたいです」 その声には微塵も刺はなく、俺は少しだけ顔をあげる。 「いつか、お願いします」 「……ん」 うん、そうだ、見たかった笑い顔はこっち。はにかむように笑う彼女を見て、俺はこくりとうなずいた。 それからお茶に誘ってくれた彼女を断り(兄ちゃんが心配してしまうから)帰路へついた。あ、あと帰り際に彼女に聞いてみたんだ、そんなに外が気になるものなのかなって。 「はい、だってわたしの知らないものがありますから。それに」 いつもとは違うものを見てみたいと彼女は笑っていた。 いつもと違うものってなんだろう。俺にとっては普通のものが彼女には不思議なものに見えたりするんだろうか。たとえばこの路地裏。煤けた壁に這う蔦だとか舗装していない道を走る子供だとか、あと凹んだバケツに張った水に映った空だとか。 「あれ?」 バケツの水の中にある空。少し灰色がかった雲は残ってるけど青くてきれいだ。だけど、そこに見慣れないものがうっすらと見えた。「あぁ」すぐにわかった。顔をあげて、それを見つめ俺は笑った。 道で遊んでいた子供も気付いて、わあわあと喜ぶ。 変わらない街の中で変わり続けるその場所。 今すぐ彼女を外へ連れ出すのは出来ないけど、いつもとは違うものを今なら見せてあげられる。 踵を返し、来た道を戻る。最初は早足だったけど気付いたら走っていた。だって早く見せてあげなきゃ! 彼女は店の中にいた。ちょうどお客さんはいなかったから、俺は早足に戻して店の中に飛び込む。 「め、メレディスさん!」 ちょっとだけ息切れしていて声が震えてたのが情けないかも。 「え、あ、ミキ、さん?」 「こっち!」 彼女の驚く顔は今日何回見たかな。俺は彼女の細い手首を緩く掴み、店の外まで連れ出す。そして上へ視線をあげ、 「ほら、あれ!」 俺が指差すと、いつもと違うそれに彼女も気付いた。 「わっ、虹!」 空に微かに見える七色。いつもとは違う空を彩る橋。彼女がどうしてあんな悲しい笑い方をするかわからないけど、もし『いつもの毎日』に飽いているせいなら。 「わざわざ教えに来てくださったんですか?」 「今すぐ外へ連れていけないから、せめていつもと違うものを見せたくて」 「……ふふっ、ありがとうございます」 「ここは変わらないけど、変わるものだってある。だから……――」 ふと気付いた。繋がれた手と、自分の言葉と。 「……あ、あの――」 慌てて手を離し素早く彼女との距離を取る。自分の尻尾が膨らんでいるのがわかって、急いで手櫛でといた。もうどうしたらいいかわからなくて、壁の後ろにかくれて、顔だけ出してみた。彼女は首をかしげていた。 「ミキさん、大丈夫ですか?」 「あ、あ……の……」 ひとつ深呼吸。壁に爪をたて、もうひとつ深呼吸。 「か、変わらない場所でも変わっていくもの、あ、ある、からっ」 「はい」 「俺が、そ、その、毎日だって見せるし教えるっ、っから、だから、悲しむことないように、あ、か、悲しまないでほしいんだ……!!」 それだけ言って、俺は彼女に背を向けた。ああもうなんだっけ、何を言いたいのかわからなくなったけど、だから、ええと、たぶんこれであってる! 彼女が後ろでなにかを言っていたみたいだけど自分の心臓の音が煩くて聞こえなかった。ああ、明日からどんな顔して会えばいいのかな! 帰ると兄ちゃんが店で寝ていたので起こしておいた。  Back Back
|
||
 |
 |