 |
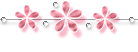 |
 |
|
-1.よく晴れた日に 初夏の事である。 その日、彼は幼馴染みと昼食を塀近くの草原で取るはずだった。だが織り手の彼女は熱を出して寝込んでしまい、自警団の彼は仕事に駆り出されてしまった。織り手、フリーダに薬を届け、自警団、ゲリーにはせっかくなので前日に作った菓子を渡した。 残ったのはミキ一人とバスケットに入った昼食。食べきれる量ではなくはないのだが、やはり一人で食べるのは寂しい。……せめて外へ行って食べることにしよう。ミキはそう決めて家を出た。 「まおー!」 家を出て町外れへと向かう彼の足に小さな子供がまとわりついた。 「まおー、あーそーぼー」 「こんにちは、ハンナ」 「こんにちは!」 よく出来ました。 ミキは笑って子供の頭を撫でた。 茶色の髪を二つに緩く結び、大きな紺色の目を輝かせる少女。ミキの小さな友人ハンナである。生まれてからまだ3年の時しか過ごしていないに関わらず、その言動は時折大人より的確である。またミキの半分にも満たない小さな身体ながら弱いものいじめを見るや否や駆け出す強い心を持っていた。 それは彼女が荒野を生きてきたから。自分の正しさを強く持ち、誰かと支え合わねば生き残れぬ世界で彼女は同じ年の子よりも多くの事を学んだのだ。 その彼女が今を街で過ごす理由。それは荒れ果てた野に生きるノラネコ特有のものである。荒野に生きるのはネコだけではない、天敵たるネズミやオオカミ達もいる。自由を得る代わりに彼らは日々生き延びる方法を考えなければならない。 しかし幾ら生きる為に頭を捻ろうと運命は彼らを別ってしまった。 彼女と彼女の親はオオカミに襲われた。命からがらに彼女は街へ逃げ込んだが、両親は身を張ってオオカミを食い止め、そのまま彼女を迎えに来る事はなかった。 そしてハンナは街に生きることになったのだ。 「ピクニック行くの?ハンナも行っていーい?」 「うん、そうしてくれると俺も嬉しいよ」 ハンナの笑みに陰りは見えない。小さな彼女は今、南門の近くにある教会の牧師夫妻と過ごしている。行き場をなくし泣いているハンナを夫妻が家族として迎え入れたのだ。最初こそぎこちなかったが、今は親子にしか見えない程に仲が良い。これからも彼女の笑みは続いていくのだろう。 「ねぇねぇ、まおー、かたぐるま!」 大きな彼を見上げズボンを引っ張るハンナ。二つ返事で返し、ミキは彼女の前に座り込んだ。程なくして背中に重みがかかり、次いで両肩にハンナの足がかかった。立ち上がる事を伝え、そろそろと膝を伸ばしていく。 「えっへっへー、まおーのかたぐるまは高ぁいね」 頭上できゃっきゃとはしゃぐ彼女が落ちないようにバスケットを持つ手の反対の手で少女の膝を押さえた。 「しゅっぱぁつ」 ハンナの笑い声混じりの掛け声と共に二人はのんびりと野原へと歩き出した。南の裏通りの住民とは皆顔見知りであるから、途中声をかけられたりお菓子を貰ったり(交換もしたり)しながら、二人は目的の場所に向かう。猥雑な裏通りを道なりに進めば、やがて風の音が聞こえるほどの静寂をたたえる草原につく。 「きれいだねぇ」 ミキの肩から降りたハンナが笑う。「ぜんぜんちがうばしょみたい」この緑萌ゆる場所も壁をひとつ隔てれば土埃舞う荒野なのだ。 二人はそのまま歩き小高い丘にある巨木まで進んだ。本来ならそこで幼馴染み達と近況を話す事になっていた場所で、またミキの好きな場所でもあった。登り道が裏通りに面しているが少し遠いせいか訪れる者はミキ達以外にはいないため静かに過ごせるのだ。そこで友人達と夢を語り、夕暮れの赤を映す街を見下ろすのがたまらなく愛しい時間であった。 はしゃぐハンナを目で追いながら、ゆるやかに登る道を進むミキがふと後ろを振り向く。耳を澄ませば街の喧騒が聞こえてくる。煩わしい事もあれど、心を落ち着かせる賑わいの、幸せが充ち満ちた町。この町の影で16年、彼は生きてきた。これからも彼は陰日向に静かに過ごすのだろう。 そんな事を考えて、浮かんできたのはメレディス・アイメルトの事だった。これまで何度か彼女の店に訪れ、なんとか友人と呼べる間柄にはなってはいるものの、無意識下にミキは彼女との間に壁を見ていた。彼自身は気にしていないつもりでいるが、時折彼の胸を痛ませるのは二人の差。光を見て彼女を想い、影に自分を見いだした。 己の想いには愚鈍なミキには痛みの理由がわからない。ただ訳にもなく哀愁を感じているのだと落ち着かせる。 彼と彼女と距離はまだ遠い。 |
||
 |
 |