 |
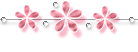 |
 |
|
-3.薬屋 ミキがハンナと共に平謝りし、男が溜め息混じりに許すことでその場は収まった。ただしゲリーについては容赦無く「決して許しはしない」眉間に深いシワを刻み、彼は虚空を睨みつける。ミキは親友の危機を感じたものの同情の余地は無いので敢えてフォローはしない。 「あ」 ミキが声を小さく声を漏らすと男が訝しげに「どうした」と声をかけた。ミキは暫し戸惑いつつも 「ゲリーをご存じなんですか」 そう問うた。 「……?君とはゲリーと一緒の時に会った事があるだろう」 「まおー、忘れん坊だもんねー」 あぐらをかいたミキの足の上で、昼食の入ったバスケットを抱いたハンナがくすくすと笑う。 「……ごめんなさい」 ミキは頭を垂れる。彼の記憶力が悪いという事はないのだが、人見知りをする為他人の顔をあまり見ず、結果、記憶に残り辛い。慣れぬ内などは会話の中でようやっと名を思い出す程である。ミキがもう一度謝罪を口にすると「構わない」彼はそう言って、微かに笑った。 「改めて、オレの名はクライヴェルグ・エイジェルステット。クライヴでいい。ギルドに務めている。あの馬鹿、ジェラルドは同期だ」 「…………」 「あの時は花をありがとう」 「…………」 「まおー、やっぱり覚えてないの?」 「…………、うん」 眉尻を下げ、肩を落とす。クライヴは、あまり話さなかったからだと言うが、どうにも申し訳がなかった。 「そんならさ、まおー。だんちょーにもお昼ご飯あげよーよ」 「え?」 まごつくミキにハンナは抱えていたバスケットを開く。 「いーっぱいあるよ!」 はしゃぎながら、ハンナはバスケットの中から銀紙に包まれたアーモンドチョコを取り出す。 「お菓子もサンドイッチも、沢山あるんだよ」 「フリーダとゲリーも来る予定だったからね」 「だんちょーにも、わけたげよー?」 小さな少女が楽しそうに笑いながら、厳つい顔の男を見上げる。男は破顔しながら小さく頷いた。 「構いませんか?」 バスケットの中から手際よく取り皿やカップを取り出しながら、ミキがクライヴに問う。 「あ、あぁ……」 「よかった!」 生返事で返すとミキはにこやかに笑う。ハンナと二人で食事の用意を始める大男の様子をクライヴはじっと観察するように見つめていた。 彼は不思議でならなかった。 以前会った時は筋骨の目立つ巨躯に見合う厳めしい顔をしかめっ面にした寡黙な男だったはずだ。長身とされるクライヴですら見上げる巨大な体躯とねめつけるような視線に一瞬でも気圧されてしまった自分を恥じていた為、ミキの事はよく覚えている。だからこそ、その違いに驚きを覚えているのだ。 他を排除しようするかのような刺々しい空気はまるでない。始終笑みを浮かべ、はしゃぐようにハンナと話している様子はまるで小さな子供のそれだ。 「こちらが本当の彼、か……?」 ぽつりと呟くのをハンナが耳敏く聞きつけ 「まおーは怖がりだから、知らない人がいると困って泣きそうな顔になっちゃうんだよ」 それをみんなは怖い顔だというのだと、ハンナがへらりと笑う。ミキは何の事かわからずに首をかしげた。 「驚いて力が抜けちゃったから、もう怖い顔しないよ。ね、まおー」 「ん?うん、そうだね」 おそらく何も分かっていない魔王はニコニコしながら、紅茶を注いだカップをクライヴに手渡す。礼を言い受け取ったカップはよく冷えており、じわりと汗をかくほどの陽気の今日には有り難かった。 「そういえば」 クライヴは落ちてきた前髪を耳にかけながら言う。 「君は花屋なのか?」 バスケットの中には来る途中に咲いていた色とりどりの花が集められており、クライヴはそれを一輪手に取る。青紫の薄い花弁をしたそれは弱い風にも散ってしまいそうなほどに儚く見え、脳裏に幼馴染みの花屋の少女が過る。 息を吐きながら花をバスケットへ戻すと同時に、ミキがサンドイッチを乗せた皿を手渡した。 「花屋ではないです。でも花が好きなので」 ハンナの分のサンドイッチを取り分けながらミキが言う。ハンナはニコニコしながらそれを受けとると、いざゆかんとばかりに手を振り上げ「手を拭かなきゃ駄目だよ」「えー……」「お手拭きあるからね」「ういー」ミキはバスケットから小さなタオルを出し、続いて出してきた小型の水筒に入れてある綺麗な水でそれを湿らせた。 「この近くの裏通りで薬屋をやってるんです。あまり流行っていませんからギルドの方は知らないと思います」 せっせとハンナの手を丁寧に拭きながら薬屋が答える。ハンナは今か今かとばかりに目を輝かせサンドイッチを見つめていた。 「薬屋か。……店名を聞いてもいいか」 「あ、はい。じゃあ」 拭き終わるや否や食べ始めた食いしん坊にエプロン代わりのハンカチを引っ掛けてやると、ミキは腰元にあったショルダーバッグから一本の硝子瓶を取り出した。クライヴがそれは何かと問えば「簡単な傷薬です」薄緑の透明な液体が入った瓶を軽くゆすってみせる。クライヴが納得したふうに一つ頷くと、ミキは更にバッグから薄茶色の紙を出しくるりと器用に巻く。そして「これ、どうぞ」それをクライヴに差し出した。 「うちの試供品です。瓶と紙に店名が書かれてますので、気に入ったら宜しくお願いします。ここらへんの人に聞けば場所が分かると思うので」 「そうか、ありがとう」 いいえ、と首を振るミキは簡単に薬の説明を始める。曰く、即効性に重点を置いたものであるが効果は弱いため、日常での使用を念頭に置いてほしいと言う。 「成分が血液に反応して凝固します。それは薄い皮膜になって傷口を被いますが、極薄いものなので大きな傷の場合は流血の力で簡単に破れてしまいます。膜で覆ったあとに更に膜が作られ……そうですね、簡単に言うと絆創膏のようになります。皮膚の再生を促す成分も入っていますので刃物での切り傷でしたら2日程で綺麗になると思いますよ」 「ジェラルドがたまに使ってるアレだな」 「あ、いえ、ゲリーのは俺が作ってる試作品です。俺はまだ見習いなので効き目は保証出来なくて……」 苦笑しながらミキはそう言ってショルダーバッグを閉じ、ハンナの手を拭いていたタオルで手をぬぐう。 「荒野へ出る方には効果の強いものもあります。ゲリーの家、えーっと、代々軍師を務めておられるグレン家の方々に昔から重用して頂いていますので効果の方には割と自信があります」 「まおー、しょーばいにん!」 「あ、う、……だって」 ミキは口ごもる。 より良いものを多くの人へ届けていきたいと彼は常々思っていた。それは自慢の父親をもっと評価してほしいという私情と、痛みで苦しむ人が一人でも減らせるようにといった純粋な善意の二つから来ている。 店の場所柄、客は専ら近所の住人である。それで生活は賄えるのだが、新規の客はここ数年居ないことをミキは不満に思っている。もっと知られていいはずだし、知ってほしいのだ。 その為、彼は常に試供の為の薬を持ち歩き宣伝の機会を探しているのだが、いかんせん人見知りの彼であるから宣伝出来た試しはない。そんな調子が続いてきた為、今ならばと思い畳み掛けてしまったのである。だが相手からすれば、がめつい商人とうつっているかもしれないのだ。ミキは恐る恐るクライヴを見て 「な、なにしてるんですか!?」 件のギルド員は短刀を引き抜き、自らの指にあてがっていた。ミキが取り上げようと手を伸ばすも虚しく、クライヴは指先を切り裂いた。ぷくりと鮮やかな朱い玉が指先に膨らむ。尻尾を膨らませて慌てるミキを横目に、当の本人は悠々と血を拭い取り先程の試供薬を傷口に振りかけた。 「なるほど、面白い」 薬をつけた傷口は瞬く間に白く薄い膜によって保護される。それによって血は止まり、また微かに感じた痛みも消えていた。彼が戦いに赴く際に持つ常備薬とは全く違う効能だ。あれはほんの気休め程度ではあるが、こちらはいわば回復魔法に近いものがある。おそらく他の薬にしても効果が軒並み高いのだろう。 「いくらだ」 「…………はい?」 「この効力ならば銀5枚か?」 「は、え……?」 「まおー、おしょーばい?」 「え、そうなんですか?」 「勿論。これだけの物を今まで知らなかった事が残念でならない」 「わっ、あっ、ありがとうございます!」 長毛の尻尾を忙しなく振り、ミキはクライヴの手を取りぎゅうと握る。強く握られ微かな痛みを感じたが、それだけ彼が喜んでいる証拠なのだろうとクライヴは笑みを返した。 「とりあえず荒野へ出る際の傷薬を10本程もらいたい。銀50枚でいいか?」 クライヴが腰のポケットから取り出した財布から銀貨を取り出す。陽光に照らされ財布の中の金銀が艶かしく煌めく。見た事の無い貨幣の数にミキは目を丸くし、食べ終えたハンナは物珍しそうに中を覗いた。 「足りないか?」 「え!?い、いえ!そんな頂けません!あ、あの、ひとつ銅10枚ですので、えっと銀を1枚頂ければ……」 「ねーねー、銅10枚で銀1枚?」 クライヴの手の中にある銀硬貨にハンナは首を傾げ、問うた。クライヴは「ハズレ。銅貨100枚で銀1枚になる」その硬貨を指先で弾き答える。 店舗の多い第二居住区では殆どが物々交換である為、貨幣というものの概念が薄い。だが物々交換の出来ない技術職や国が直々に雇っている場合は貨幣によって支払われる事が多い。ミキの店でも基本的に物々交換ではあるが時折貨幣で払うネコもおり(単に物珍しく楽しいからという理由だが)一応の値段はつけられていた。父が付けた価格が妥当かどうかはミキにはわからないが、兄は不満気に鼻を鳴らしていた。そんな事を思い出していた為 「そんなに安いのか?」 訝しげにこちらを見やる美丈夫の言葉に一人ミキは納得した。 街で売られている小麦パンは銅貨4枚であるから、ミキの店の薬はパン2つ相当でしかない。クライヴが買っていた薬はおおよそ銅50枚であるから、この効果からすれば破格値であるといっても過言ではないのだ。 「基本的に薬草は荒野で取ってきますので材料費はただなんです。それに、お金より誰かの怪我が治る方が嬉しいじゃないですか」 どうせお金なんてあっても使わないし、とミキは笑う。ふぅんとクライヴは頷き銀貨を1枚ミキへと渡した。 クライヴは第一居住区に住むネコである。比較的裕福な層に生まれ、幼い頃から貨幣によって動く労働者を見てきた。その為、貨幣の価値、つまり物の価値についてはそれなりに心得ており、ミキが言う言葉には首を捻るばかりである。クライヴは万の金が当たり前に存在する環境に慣れてしまい重要性が薄れがちではあったが、貨幣は多く持っていた方が有利である事は常識として知っている。貨幣の価値は概ね一定だ。草臥れはするが腐りはしないし、失わなければ消えもしない。第2居住区で行われる物々交換のあやふやな価値の交換はまさに未知であり、不可解である。腐らないものだとしても古びたり使用したりで価値が下がっていくばかりだ。それならば一定の価値を持つ貨幣を貯めた方が良いのではないか。 「金はあった方がいいと思うが」 無いよりいい。 それを薬屋に言えば、彼は少し考えたふうに顎に指を当てる。 「無くても生きていけるなら無い方がいいと思います」 「何故?」 「だって頼ってしまいそうじゃないですか、こんなちっちゃい物に。互いに足りない所を補いあうだけで生きていけるなら、それでいいと思うんです」 ミキは言う。 「誰かが風邪をひいたら俺は風邪薬を届けにいきます。別にお金、えっと、利益が欲しいからじゃありません。ただその人が困ってるからです。その時、風邪引いてる人が俺がスプーンを無くしたのを知っていたとして、その人は風邪薬の代わりにスプーンをくれました。ここにはお金の取引はありません。誰かを想う心を交換しただけ。得はしましたが誰も損はしていません」 胸に手をあてミキは微笑む。大人同士の会話に退屈したハンナはバスケットからクッキーを取りだしミキの隣で頬張りだした。 「お金がダメなものなんて言いませんけど、なんだか寂しいんです。お金っていうものが相手の気持ちを隠す壁になっているような気がして」 「……壁か」 「価値の変わらないお金は大事だって母さんは言うんですけど、同時に変わらない物っていうのにひとは頼りがちになるんだって言うんです。だから、きっといつかは貨幣で回る世界になる。でも今はまだ大丈夫だから、人と壁を作るものに頼る生き方はしたくないな、なんて思うんです」 「なるほど」 クライヴは感慨深げに頷く。ミキは照れ臭そうに笑い「偉そうに言ってすいません」頭を下げた。 「いや、興味深い話を有難う。オレの想像の及ばない話だったよ」 「いえ、あの、そんな……」 「ねー、おはなし終わり?だんちょー、食べないの?」 口の端に焼き菓子の欠片をつけた小さな少女がクライヴの足に置かれた小皿のサンドイッチを指差す。 「ちゃんと食べないとおっきくなれないんだよ。食べないとまおーが怒るんだからねー」 「そうか、それは大変だ」 ミキに目を向けると何か言いたげに首をかしげて苦笑している。「じゃあ」 いただきます。 静かに剣士は手を合わせ、魔王もそれに倣う。少女は満足そうに笑うと再びバスケットに手を突っ込み菓子を取りだし―― 「もっとごはん食べなきゃダメだよ」 視界を遮る大きな手にはサンドウィッチの乗った小皿。ハンナは頬を膨らませながらも渋々受けとった。 |
||
 |
 |